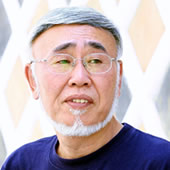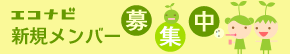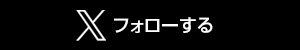- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 集まる
- 地域の健康診断
- 059 水の国ニッポンを支える「見えない山」
0592025.11.25UP水の国ニッポンを支える「見えない山」
道志村から考える、私たちの水資源
山梨県道志村は県の最南端に位置し、北は道志山塊、南は丹沢山塊に抱かれた、山林率95%の山村です。古くから「道志七里」と呼ばれ、旧道の一里ごとに塚が置かれていたといいます。
現在は東西約28キロの村を、カーブが連続する国道413号線が貫いています。道の途中には富士山の眺望ポイントもあり、ライダーの人気スポットにもなっています。
筆者は江戸時代建築の農家民宿「北の勢堂」に宿泊し、村を案内していただきました。
「道の駅どうし」で『道志七里』(伊藤堅吉著、柳田國男序)の復刻版を手にしましたが、清流と共に生きてきた村人の誇りが静かに伝わってきました。
横浜の水は、道志の山から
明治30年、村の中央を流れる道志川から、横浜市の水道水の取水が始まりました。
やがて大正5年、横浜市は山梨県から県有林2,780haを購入し、水源涵養林として経営を開始。今日も横浜市水道局の職員が現地に派遣され、人工林の間伐による水源かん養機能の向上や全国的に拡大しているナラ枯れ被害の調査・対策など山の保全にあたっています。
村には今も、「明治政府が横浜港開港のために我が山を取った」という思いを抱く人もいます。
実際には開港の後の水道事業のため直接の関係はありませんが、「おらが山が神奈川県のものになった」という感情は、地域の記憶として語り継がれているようで、山は人々の誇りであり、心の拠り所であったことが伺えます。
水を育てる森、森を守る人
今日、日本各地の山村は人口減少に直面し、山林の維持はおろか、集落機能すら危うくなっています。道志村の森林が今も保たれているのは、横浜市という大都市が水源地として継続的に支えてきたことによる面もあることを思うと、今となれば村にとっても良かったのかもしれません。
全国を見渡すと、上下流が手を取り合う新しい試みも広がっています。
長野県根羽村では、下流の愛知県安城市などと「矢作川水源の森」環境育成協定を締結。人工針葉樹林を針広混交林に転換するなど、森の多様性を回復させています。この取り組みは熊の出没抑制にもつながることをめざすと同時に環境教育の場として次世代への継承にもつながっているようにも感じます。
長野県木曽町・大滝村では、愛知県大府市と「水源の森林保全協定」を結び、上流で伐採された木材を下流域の公共施設に利用。木曽川を介した“森と水の循環”を実現しています。
上流と下流、都市と山村は運命共同体
近年、半導体製造などで地下水を大量に汲み上げる企業が増えています。こうした事業者から「地下水利用協力金」を徴収し、水源地保全や上流域支援に充てる自治体も登場しました。
水を巡る経済と環境の新しい関係が、静かに動き始めているのです。
都市の蛇口をひねると出る水は、遠い山の森が、時間をかけて育てた“贈り物”です。
下流の都市は上流の山村に支えられ、山村は都市からの支援で息をつなぐことができる運命共同体なのです。
雨の国・水をめぐる共生の未来へ
日本の年間平均降水量は約1,700mm。世界平均(約970mm)の1.7倍もあり、「水の豊かな国」と言われます。
しかし降る時期や場所が偏っていること、梅雨や台風による豪雨が急峻な地形のため一気に河川へ流れ込むこと、また近年の異常気象も影響して、上流域の土砂崩れや下流域の冠水などの水害が頻発・激甚化しています。
それでも森林は、雨をゆっくりと抱き込み、やがて清らかな水となって湧き出しています。この自然の循環があるからこそ、日本は世界でも数少ない「水道水をそのまま飲める国」となっているのです。老朽化した水道管が破裂して断水すれば、そのありがたみをすぐに思い知らされることでしょう。
日本の一人当たりの水資源量は世界平均のわずか4分の1で、実は決して“水に余裕がある国”ではありません。2024年、日本はミネラルウォーターを年間約25万キロリットルも輸入しました。それは “国内の水環境への不安”が消費者心理に働いているのかもしれません。
水は誰かの所有物ではなく、地域と地域、人と人をつなぐ共有資源です。
道志村の山々が今も横浜の街を潤すように、上流と下流が互いに支え合う仕組みを築くことが、これからの日本に欠かせません。
大都市からは“見えない山”に、私たちの暮らしは支えられているのです。その事実を忘れずに、次の世代へと水と森のバトンを渡してほしいと願っています。
バックナンバー
- 001「地域を元気にする=観光地化ではない」
- 002「地域を元気にする=一村一品開発すればいいわけではない」
- 003「地域を元気にする=自ら考え行動する」
- 004「縦割りに横串を差す」
- 005「集落の元気を生産する「萩の会」」
- 006「小学生が地域を育んだ」 -広島県庄原市比和町三河内地区-
- 007「山古志に帰ろう!」
- 008「暮らしと産業から思考する軍艦島」
- 009「休校・廃校を活用する(1)」
- 010「休校・廃校を活用する(2)」
- 011「アートで地域を元気にする」
- 012「3.11被災地のまちではじまった協働の復興プロジェクト」
- 013「上勝町と馬路村を足して2で割った古座川町」
- 014「儲かる農業に変えることは大切だが、儲けのために農家が犠牲になるのは本末転倒」
- 015「持続する過疎山村」
- 016「したたかに生きる漁村」
- 017「飯田城下に地域人力車が走る」 -リニア沿線の人力車ネットワークをめざして-
- 018「コミュニティカフェの重要性」
- 019「伝統野菜の復興で地域づくり」 -プロジェクト粟の挑戦-
- 020「地元学から地域経営へ 浜田市弥栄町の農村経営」
- 021「持続する『ふるさと』をめざした地域の創出に向けて」
- 022「伊勢木綿は産業として残す」
- 023「北海道最古のリンゴ「緋の衣」」
- 024「風土(フード)ツーリズム」
- 025「ゆきわり草ヒストリー」
- 026「活かして守ろう 日本の伝統技術」
- 027「若い世代の帰島や移住が進む南北約160kmの長い村」 -東シナ海に浮かぶ吐喝喇(トカラ)列島(鹿児島県鹿児島郡十島村)-
- 028「徹底した子どもへの教育・子育て支援で過疎化の危機的状況を回避(高知県土佐町)」
- 029「農泊を再考する」
- 030「真鯛養殖日本一の愛媛県の中核を担う、宇和島の鯛(愛媛県宇和島市遊子水荷浦)」
- 031「一人の覚悟で村が変わる」 -京都府唯一の村、南山城村-
- 032「遊休資産が素敵に生まれ変わる」
- 033「福祉分野が雇用と関連ビジネスの宝庫になる」 -飯田市千代地区の自治会による保育園運営の取組-
- 034「日本のアマルフィの石垣景観を守る取り組み」 -愛媛県伊予町-
- 035「アニメ・ツーリズム」
- 036「おいしい田舎「のどか牧場」」
- 037「インバウンドの苦悩」
- 038「コロナ禍後の未来(1)」
- 039「コロナ禍後の未来(2)」
- 040「MaaSがもたらす未来」
- 041「二人の未来は続いてゆく」 -今治市大三島-
- 042「ワーケーションは地域を救えるか」
- 043「アフター・コロナの処方箋は地域のダイエット」
- 044「ヒトを呼ぶパワー(前編)」
- 045「ヒトを呼ぶパワー(後編)」
- 046「地域の価値創造」 -サスティナブル・ツーリズム-
- 047「廃校活用の未来」
- 048「小田原なりわいツーリズム」
- 049「地産地消エネルギーで地域自立する」
- 050「地域丸ごと地球の学び舎」
- 051「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(1)」
- 052「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(2)」
- 053「夢にチャレンジできるまち、実現できるまち」
- 054「新たな福祉コミュニティ」
- 055「「食料・農業・農村基本法」の改正は食料安全保障の強化!?」
- 056「香春町採銅所が紡ぐ地域コミュニティ」
- 057「水こそ命」
- 058「瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦」
- 059「水の国ニッポンを支える「見えない山」」
- 060「気候変動が生活困難の要因になる」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.