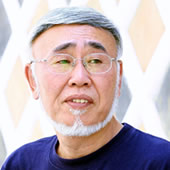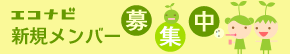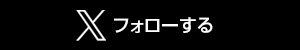- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 集まる
- 地域の健康診断
- 057 水こそ命
0572025.05.13UP水こそ命
いのちの根源を見つめて
先日、秩父市の上流、小鹿野町を視察する中で、あるダムの姿に目を奪われました。水面を見た瞬間、胸に走ったのは「少ない!」という直感。目の前に広がっていたのは、他地域なら確実に“水不足”と報道される深刻な状況でした。
とりわけ今は田植えの時期。田に水を引けなければ、稲作は成り立ちません。作付け不能となれば、今年も「米騒動」が現実のものとなる恐れがあります。小鹿野町自体は水田が少なく、また荒川流域には豊かな森林が広がっているため、現時点では深刻な危機感は覚えません。しかし、都市部の水道水の行方はどうでしょうか。今年、東京都内で「節水協力」のアナウンスがなされることは、ほぼ確実だと言えるでしょう。
地球は「水の惑星」と呼ばれていますが、人類が利用できる淡水は、全体のわずか0.01%と驚くほど少ないのです。日本は世界平均の2倍の降水量を誇り「水に恵まれた国」として知られています。それが私たちの「水不足」の意識を鈍らせているのでしょう。
しかし日本の国土はご存知の通り、山がちで急峻。降り注いだ雨は短時間で河川を駆け下り、あっという間に海へと流れ去ってしまいます。その結果、実際に私たちが利用できる一人当たりの水資源量は、世界平均の半分以下に過ぎません。
それでも多くの国民が水不足を感じないのは、私たちが大量の「バーチャルウォーター(仮想水)」を輸入しているからです。東京大学生産技術研究所の試算によれば、日本が1年間に消費する水の総量約800億立方メートルのうち、その8割に相当する640億立方メートルを、私たちは食品や製品のかたちで海外から“間接的に”輸入しているのです。
2050年には、世界の人口が90億人を超えるとされています。水資源をめぐる争い、水の奪い合い、いわゆる「水戦争」が現実となれば、今は見えない水の価値が、かつてないほど高騰するでしょう。
たとえば、世界人口の約20%を抱える中国が保有する水資源は、わずか6%に過ぎません。急激な工業化により、農地の20%が汚染され、水不足はさらに深刻化しています。だからこそ、中国資本による日本の山林や水源地の買収がニュースとして報じられるようになったのです。世界は、すでに水をめぐる争奪戦の真っただ中にあるのです。
私たち日本人にとっても、この「世界の水危機」は決して他人事ではありません。食料自給率が低く、かつ水資源に乏しい日本は、むしろ真っ先に追い詰められる立場にあるのです。
人と自然が響きあう風景
今回私が訪れた秩父の中山間地域には、人と自然の美しき共生の記憶が残っていました。新緑はまるで“神緑”とでも称したくなるほどの生命力を放ち、人工林でありながら、スギやヒノキの暗い森とは一線を画した明るさがありました。
かつてこの地の人々は、炭焼きで生計を立てていました。その営みが残した薪炭林は、今や美しい景観として地域の財産となっています。そして、こうした多様性に富んだ森こそが、荒川の源流域として豊かな水を蓄え、埼玉県民や東京都民の命を支える「水源」となっているのです。
かの田中正造は、足尾銅山鉱毒事件において命をかけて環境を守り、「真の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を壊さず」と喝破しました。この言葉は今もなお、私たちの胸に深く刻まれるべきでしょう。
日本の歴史と文化は、農と林に支えられ、「水」とともに築かれてきました。いわゆる「手つかずの自然」と標榜する自治体もありますが、実際には多くの山林が、古来より人々の手によって育まれてきた“文化的自然”なのです。そうした事実を単に享受するだけではなく、きちんと理解し、尊重しなければなりません。
先人が苦労の末に築き上げた自然の果実を、私たちは無為に消費するのではなく、守り、次世代へと確実に引き継いでいく責任があります。
美しい風景に惹かれて旅をする。そうした旅人を惹きつける地域には、豊かな自然と人の温もりが共存しています。インバウンドが熱を帯びるいま、日本が単に“消費される観光地”になるのではなく、独自の歴史や文化、自然への配慮を活かしたエコツーリズムやサステナブル・ツーリズムへと舵を切ることが、未来の観光の在り方ではないでしょうか。
毎年1月~5月末及び9月~10月末に実施される緑の募金運動は、特に4月から5月のみどりの月間に重点的に展開されています。新緑の季節、行楽に訪れるその先で、どうか森の環境に目を向け、ほんの少しでいいので、思いを馳せていただければ幸いです。
バックナンバー
- 001「地域を元気にする=観光地化ではない」
- 002「地域を元気にする=一村一品開発すればいいわけではない」
- 003「地域を元気にする=自ら考え行動する」
- 004「縦割りに横串を差す」
- 005「集落の元気を生産する「萩の会」」
- 006「小学生が地域を育んだ」 -広島県庄原市比和町三河内地区-
- 007「山古志に帰ろう!」
- 008「暮らしと産業から思考する軍艦島」
- 009「休校・廃校を活用する(1)」
- 010「休校・廃校を活用する(2)」
- 011「アートで地域を元気にする」
- 012「3.11被災地のまちではじまった協働の復興プロジェクト」
- 013「上勝町と馬路村を足して2で割った古座川町」
- 014「儲かる農業に変えることは大切だが、儲けのために農家が犠牲になるのは本末転倒」
- 015「持続する過疎山村」
- 016「したたかに生きる漁村」
- 017「飯田城下に地域人力車が走る」 -リニア沿線の人力車ネットワークをめざして-
- 018「コミュニティカフェの重要性」
- 019「伝統野菜の復興で地域づくり」 -プロジェクト粟の挑戦-
- 020「地元学から地域経営へ 浜田市弥栄町の農村経営」
- 021「持続する『ふるさと』をめざした地域の創出に向けて」
- 022「伊勢木綿は産業として残す」
- 023「北海道最古のリンゴ「緋の衣」」
- 024「風土(フード)ツーリズム」
- 025「ゆきわり草ヒストリー」
- 026「活かして守ろう 日本の伝統技術」
- 027「若い世代の帰島や移住が進む南北約160kmの長い村」 -東シナ海に浮かぶ吐喝喇(トカラ)列島(鹿児島県鹿児島郡十島村)-
- 028「徹底した子どもへの教育・子育て支援で過疎化の危機的状況を回避(高知県土佐町)」
- 029「農泊を再考する」
- 030「真鯛養殖日本一の愛媛県の中核を担う、宇和島の鯛(愛媛県宇和島市遊子水荷浦)」
- 031「一人の覚悟で村が変わる」 -京都府唯一の村、南山城村-
- 032「遊休資産が素敵に生まれ変わる」
- 033「福祉分野が雇用と関連ビジネスの宝庫になる」 -飯田市千代地区の自治会による保育園運営の取組-
- 034「日本のアマルフィの石垣景観を守る取り組み」 -愛媛県伊予町-
- 035「アニメ・ツーリズム」
- 036「おいしい田舎「のどか牧場」」
- 037「インバウンドの苦悩」
- 038「コロナ禍後の未来(1)」
- 039「コロナ禍後の未来(2)」
- 040「MaaSがもたらす未来」
- 041「二人の未来は続いてゆく」 -今治市大三島-
- 042「ワーケーションは地域を救えるか」
- 043「アフター・コロナの処方箋は地域のダイエット」
- 044「ヒトを呼ぶパワー(前編)」
- 045「ヒトを呼ぶパワー(後編)」
- 046「地域の価値創造」 -サスティナブル・ツーリズム-
- 047「廃校活用の未来」
- 048「小田原なりわいツーリズム」
- 049「地産地消エネルギーで地域自立する」
- 050「地域丸ごと地球の学び舎」
- 051「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(1)」
- 052「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(2)」
- 053「夢にチャレンジできるまち、実現できるまち」
- 054「新たな福祉コミュニティ」
- 055「「食料・農業・農村基本法」の改正は食料安全保障の強化!?」
- 056「香春町採銅所が紡ぐ地域コミュニティ」
- 057「水こそ命」
- 058「瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦」
- 059「水の国ニッポンを支える「見えない山」」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.