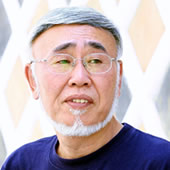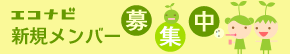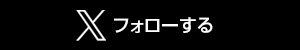- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 集まる
- 地域の健康診断
- 058 瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦
0582025.08.05UP瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦
瀬戸内海の歴史と現状
瀬戸内海は、入り組んだ入江や湾が特徴の閉鎖性海域で、古くから漁業が盛んな地域です。
しかし、高度経済成長期には人口集中と工場の増加、臨海部の埋立てが進んだことで水質が悪化し、赤潮の発生が増加。結果、多くの魚介類が死滅する深刻な事態が発生しました。
1970年代には水質汚濁による「富栄養化」が深刻化。1978年の水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特措法の改正により水質総量削減制度が導入され、環境の回復に取り組んでいます。
魚介類の生育地や渡り鳥の休息地として重要な藻場や干潟は埋立て等によって大きく減少してきました。藻場のうちアマモ場については、1960年度から1989-90年度までに約7割、干潟については1989年度から2015-2017年度までに約5割が消失しました。
一度損なわれた美しい海の景観と豊穣なる海を完全に取り戻すには、いまだ多くの困難が横たわっております。
広島湾の貧栄養化とプラスチック問題
近年、広島湾では山から海へ養分供給を行うため「漁民の森づくり」を行っています。一方で、藻場の消失による磯焼け、さらに海洋プラスチックごみやマイクロプラスチックの流入が、湾内の生態系に深刻な影響を及ぼしています。
広島県は、日本屈指の牡蠣の産地として知られています。その養殖においては、ホタテ貝の殻に牡蠣の種苗を付着させ、筏から吊るすための「スペーサーパイプ」と呼ばれる長さ21~24cm、内径1cmほどのプラスチック製の器具が用いられてきました。広島湾では、およそ3億本にのぼるプラスチック製パイプが使用されていると見られ、破損や事故によって海中へ流出し、漂流・漂着ごみとして大きな問題となっています。
広島かき生産対策協議会は、流出して海岸に漂着したプラスチック製パイプを一定価格で買取る制度を設けていますが、道具の劣化や廃棄の管理不足により流出が後を絶たず、課題は根深いものがあります。しかも、これらのプラスチックは、自然環境下で分解されるまでに400年から1000年を要するとされ、世界的にも喫緊の環境課題と位置づけられております。
筆者はこうした“見えざる”海のプラスチック汚染の実態を初めて知り、新たな解決策が早急に必要だとの思いを強くしました。
持続可能な未来を切り開く「山海環(さんかいかん)」の挑戦
2021年4月、「里山」と「里海」の環境再生と資源循環を目指して「山海環(さんかいかん)」が設立されました。その活動は、竹と炭を活用して里山と里海をつなぐ循環型社会の構築を掲げ、次の3つの柱を中心に取り組んでいます。
① 牡蠣養殖用プラスチックパイプの「竹」への転換
② 廃棄された牡蠣いかだの竹材の「炭化」
③ 広島県産竹材の養殖資材としての「普及拡大」
現在、海中で使用されているスペーサーパイプは、いかだ1台あたり約24,000本。広島県内には約12,000台のいかだが存在し、合計でおよそ3億本にのぼるパイプが使用されている計算になります。
「山海環」では、このプラスチックパイプを自然由来の「篠竹(しのだけ)」に置き換える試みを開始しました。篠竹は河川法面や河川敷に繁茂し、防災上問題視されることもある一方で、生分解可能で、使用後には焼却や炭化も可能な資源です。この竹を24cmにカットし、節を抜きパイプとして再利用。地元の養殖業者と連携し、実証実験を進めています。
ただし、篠竹の安定供給や耐久性、コスト面に課題があるため、さらに持続可能な素材開発が模索されています。
炭化技術と循環モデルの確立へ
「山海環」は現在、炭化技術を応用し、使用済みの竹や木材を粉砕・成形した「再生型パイプ」の開発に着手。プラスチックに竹炭や竹パウダーを25%配合した「バイオプラスチック」製品を開発し、2023年から実証実験をスタートしています。
また、現在は野焼き処分されている廃いかだを竹炭として再利用し、当面年間24トン程度のバイオ炭を生成し、将来は年100トンの焼成を目指すとともに竹炭や竹パウダーの配合比率を高めた生分解性バイオプラスチックとして、真の循環型システムの構築に向けて動き出しました。
「山海環」は、猛暑のなかでも炭を焼き続けながら、未利用資源の活用と環境保全に全力で取り組んでいます。プラスチック依存から脱却し、自然と共生する持続可能な養殖業の未来を切り開くこの挑戦は、瀬戸内海の再生と日本の環境モデルに大きな希望をもたらすことが期待されます。
バックナンバー
- 001「地域を元気にする=観光地化ではない」
- 002「地域を元気にする=一村一品開発すればいいわけではない」
- 003「地域を元気にする=自ら考え行動する」
- 004「縦割りに横串を差す」
- 005「集落の元気を生産する「萩の会」」
- 006「小学生が地域を育んだ」 -広島県庄原市比和町三河内地区-
- 007「山古志に帰ろう!」
- 008「暮らしと産業から思考する軍艦島」
- 009「休校・廃校を活用する(1)」
- 010「休校・廃校を活用する(2)」
- 011「アートで地域を元気にする」
- 012「3.11被災地のまちではじまった協働の復興プロジェクト」
- 013「上勝町と馬路村を足して2で割った古座川町」
- 014「儲かる農業に変えることは大切だが、儲けのために農家が犠牲になるのは本末転倒」
- 015「持続する過疎山村」
- 016「したたかに生きる漁村」
- 017「飯田城下に地域人力車が走る」 -リニア沿線の人力車ネットワークをめざして-
- 018「コミュニティカフェの重要性」
- 019「伝統野菜の復興で地域づくり」 -プロジェクト粟の挑戦-
- 020「地元学から地域経営へ 浜田市弥栄町の農村経営」
- 021「持続する『ふるさと』をめざした地域の創出に向けて」
- 022「伊勢木綿は産業として残す」
- 023「北海道最古のリンゴ「緋の衣」」
- 024「風土(フード)ツーリズム」
- 025「ゆきわり草ヒストリー」
- 026「活かして守ろう 日本の伝統技術」
- 027「若い世代の帰島や移住が進む南北約160kmの長い村」 -東シナ海に浮かぶ吐喝喇(トカラ)列島(鹿児島県鹿児島郡十島村)-
- 028「徹底した子どもへの教育・子育て支援で過疎化の危機的状況を回避(高知県土佐町)」
- 029「農泊を再考する」
- 030「真鯛養殖日本一の愛媛県の中核を担う、宇和島の鯛(愛媛県宇和島市遊子水荷浦)」
- 031「一人の覚悟で村が変わる」 -京都府唯一の村、南山城村-
- 032「遊休資産が素敵に生まれ変わる」
- 033「福祉分野が雇用と関連ビジネスの宝庫になる」 -飯田市千代地区の自治会による保育園運営の取組-
- 034「日本のアマルフィの石垣景観を守る取り組み」 -愛媛県伊予町-
- 035「アニメ・ツーリズム」
- 036「おいしい田舎「のどか牧場」」
- 037「インバウンドの苦悩」
- 038「コロナ禍後の未来(1)」
- 039「コロナ禍後の未来(2)」
- 040「MaaSがもたらす未来」
- 041「二人の未来は続いてゆく」 -今治市大三島-
- 042「ワーケーションは地域を救えるか」
- 043「アフター・コロナの処方箋は地域のダイエット」
- 044「ヒトを呼ぶパワー(前編)」
- 045「ヒトを呼ぶパワー(後編)」
- 046「地域の価値創造」 -サスティナブル・ツーリズム-
- 047「廃校活用の未来」
- 048「小田原なりわいツーリズム」
- 049「地産地消エネルギーで地域自立する」
- 050「地域丸ごと地球の学び舎」
- 051「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(1)」
- 052「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(2)」
- 053「夢にチャレンジできるまち、実現できるまち」
- 054「新たな福祉コミュニティ」
- 055「「食料・農業・農村基本法」の改正は食料安全保障の強化!?」
- 056「香春町採銅所が紡ぐ地域コミュニティ」
- 057「水こそ命」
- 058「瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦」
- 059「水の国ニッポンを支える「見えない山」」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.