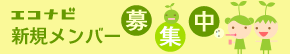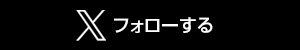- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 集まる
- 地域の健康診断
- 007 山古志に帰ろう!
0072012.10.30UP山古志に帰ろう!
過疎高齢化の山里を襲った災厄
東日本大震災から1年8ヶ月が経過しました。各自治体により復興のスピードはまちまちで、地域力の差がそのまま出ています。
今から遡ること8年前の2004年10月23日、新潟県中越地方を震源に最大震度7の大地震が襲いました。日本有数の地すべり地帯である山古志村(現長岡市)は、家屋倒壊だけでなく地滑りにより村外に通じる全ての交通が遮断され、ヘリコプターで全村避難を余儀なくされました。このとき村民のほとんどは、上空からふるさとの惨状を見て、二度と村には帰れないと覚悟を決めたのです。しかし「山古志に帰ろう」を合い言葉に、僅か3年で約7割の村民がふるさとに帰りました。震災前より人口2千人程度で過疎高齢化が進んでおり、震災では「錦鯉」生産の主要産業が壊滅しました。そんな状況を乗り越えて、人口3割減で踏みとどまったことは、他地域の過疎高齢化が進む地域でどう行動すれば良いかという羅針盤となります。
自立力が養われていた村民
3m以上の積雪を記録する豪雪地で生き抜くため、力を合わせて暮らす重さを村民は自覚していました。この相互扶助や自立の考え方は、昭和55年から行った酒井省吾村長の“企画も村民、実行も村民”の村づくりでしょう。ここから皆で考え結束して生きることや自分が生まれ育った村に誇りを持ち、急激な過疎化を食い止め「かけがいのない村」を愛し守ろう、発展させようとする“村民の意志”が育まれました。そうした村づくり精神が国重要無形文化財に指定された「牛の角突き」や世界的に有名な錦鯉、美しい棚田の復活・再生だったのです。被災後、直ちに誰に言われ頼まれたわけではなく行動を開始した村民の成果だと言えます。
復興へのプロセスを辿る中で、震災前の2004年に開設した3カ所の小さな直売所が村民の帰村と連動しました。全村避難が解除された2007年以降も毎年開設され、2012年には13カ所となっています。復興の活力が満ちていったことが窺えますが、ミニ直売所が急増したキーワードは「恩返し」と「コミュニティ」です。
村民は、復旧・復興のボランティアや様子を見に来てくれた人に、お茶や食べ物を出したい、自分たちが元気ですと伝えたい、全国の支援者に対して恩返しをしたいという気持ちだったそうです。
一方で、コミュニティの再構築も火急の用でした。救援物資を分ける拠点が自然発生的に地場の野菜等を扱う場所になりました。
「自分が避難先から帰村した時は3軒しか住んでいなかった。皆、食べ物を取りに来いよと声をかけて励まし合う場だったのがこの直売所」
そう話すように復興の際の集落コミュニティの再生として生まれたのです。
人は「土」に生きる
人間は「土」に触れていることで生きられるということが仮設住宅暮らしで証明されました。
避難生活で心が折れかけたとき「こんな事じゃいけない。なんとか前を向こう」と、仮設住宅前で野菜を植え収穫を始めました。やがて仮設住宅付近の農地を借りて作るまでに至るのですが、食べる物を共につくることで艱難辛苦に立ち向かったのです。絶対に生きて村に帰るという信念は、まずは自分が心身共に健康でなければいけないと考えた結果であり決意の顕れでした。
この成果は東日本大震災で仮設住宅暮らしをする高齢者に活きました。避難生活で心肺機能低下や歩行困難、鬱などの症状を引き起こす「生活不活発病」の防止に効果があると、仮設住宅周辺の農地を借りて耕作をはじめたのです。
復旧・復興を進めた人々の精神的よりどころは、自己の存在意義を見出すための農産物の生産販売と都市部から嫁いできた女性たちが「この村の人は温かい。困ったことをいつでも相談できる」というコミュニティへの帰属意識であったのでしょう。
このように地域づくりが成果を上げ、村外からの受入や直売所などで成功したかに見えます。しかし、次世代の若者たちが帰ってきて暮らしが成立するだけの経済的な豊かさに至らず、過疎高齢化は止まっていません。このことは全国の地域が内包しているもので、東日本大震災の被災地や放射能汚染という二重の苦しみにある福島県にとって、地域・集落の共同の労働や暮らしの場を蘇らせること、地域文化を復活させられるかが重く大きな課題です。
バックナンバー
- 001「地域を元気にする=観光地化ではない」
- 002「地域を元気にする=一村一品開発すればいいわけではない」
- 003「地域を元気にする=自ら考え行動する」
- 004「縦割りに横串を差す」
- 005「集落の元気を生産する「萩の会」」
- 006「小学生が地域を育んだ」 -広島県庄原市比和町三河内地区-
- 007「山古志に帰ろう!」
- 008「暮らしと産業から思考する軍艦島」
- 009「休校・廃校を活用する(1)」
- 010「休校・廃校を活用する(2)」
- 011「アートで地域を元気にする」
- 012「3.11被災地のまちではじまった協働の復興プロジェクト」
- 013「上勝町と馬路村を足して2で割った古座川町」
- 014「儲かる農業に変えることは大切だが、儲けのために農家が犠牲になるのは本末転倒」
- 015「持続する過疎山村」
- 016「したたかに生きる漁村」
- 017「飯田城下に地域人力車が走る」 -リニア沿線の人力車ネットワークをめざして-
- 018「コミュニティカフェの重要性」
- 019「伝統野菜の復興で地域づくり」 -プロジェクト粟の挑戦-
- 020「地元学から地域経営へ 浜田市弥栄町の農村経営」
- 021「持続する『ふるさと』をめざした地域の創出に向けて」
- 022「伊勢木綿は産業として残す」
- 023「北海道最古のリンゴ「緋の衣」」
- 024「風土(フード)ツーリズム」
- 025「ゆきわり草ヒストリー」
- 026「活かして守ろう 日本の伝統技術」
- 027「若い世代の帰島や移住が進む南北約160kmの長い村」 -東シナ海に浮かぶ吐喝喇(トカラ)列島(鹿児島県鹿児島郡十島村)-
- 028「徹底した子どもへの教育・子育て支援で過疎化の危機的状況を回避(高知県土佐町)」
- 029「農泊を再考する」
- 030「真鯛養殖日本一の愛媛県の中核を担う、宇和島の鯛(愛媛県宇和島市遊子水荷浦)」
- 031「一人の覚悟で村が変わる」 -京都府唯一の村、南山城村-
- 032「遊休資産が素敵に生まれ変わる」
- 033「福祉分野が雇用と関連ビジネスの宝庫になる」 -飯田市千代地区の自治会による保育園運営の取組-
- 034「日本のアマルフィの石垣景観を守る取り組み」 -愛媛県伊予町-
- 035「アニメ・ツーリズム」
- 036「おいしい田舎「のどか牧場」」
- 037「インバウンドの苦悩」
- 038「コロナ禍後の未来(1)」
- 039「コロナ禍後の未来(2)」
- 040「MaaSがもたらす未来」
- 041「二人の未来は続いてゆく」 -今治市大三島-
- 042「ワーケーションは地域を救えるか」
- 043「アフター・コロナの処方箋は地域のダイエット」
- 044「ヒトを呼ぶパワー(前編)」
- 045「ヒトを呼ぶパワー(後編)」
- 046「地域の価値創造」 -サスティナブル・ツーリズム-
- 047「廃校活用の未来」
- 048「小田原なりわいツーリズム」
- 049「地産地消エネルギーで地域自立する」
- 050「地域丸ごと地球の学び舎」
- 051「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(1)」
- 052「廃校活用の可能性と持続可能な社会への貢献(2)」
- 053「夢にチャレンジできるまち、実現できるまち」
- 054「新たな福祉コミュニティ」
- 055「「食料・農業・農村基本法」の改正は食料安全保障の強化!?」
- 056「香春町採銅所が紡ぐ地域コミュニティ」
- 057「水こそ命」
- 058「瀬戸内海の環境を守る「山海環(さんかいかん)」の挑戦」
- 059「水の国ニッポンを支える「見えない山」」
- 060「気候変動が生活困難の要因になる」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.