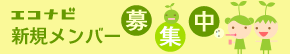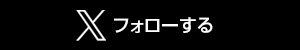- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 学ぶ
- 自然を守る仕事
- 030 子ども一人一人の考えや主張を尊重・保障する、“見守り”を大事に
0302019.11.05UP子ども一人一人の考えや主張を尊重・保障する、“見守り”を大事に-自然学校スタッフ・星野陽介さん-
磯辺の潮溜まりで小さな魚やカニを捕まえ、波間に浮かんで泳ぐ一日

星野陽介(ほしのようすけ)さん
1987年5月、東京都目黒区生まれ。
NPO法人もあなキッズ自然楽校スタッフ。
高校卒業後、英語をしゃべれるようになりたいとの思いで、カナダの大学に進学。General Studies(教養学)専攻。卒業を機に帰国して、奨学金の返済と学費を貯めるための1年間のアルバイト生活を経て、2010年4月に東京環境工科専門学校の自然環境保全学科に入学。第19回で紹介した三瓶雄士郎さんは同期。
専門学校を卒業して、沖縄でカヤックやスノーケルのガイド・インストラクターとして3年半ほど働いたあと、2015年から「もあなキッズ自然楽校」に採用され、現在に至る。
海の近くに住みたいと、平塚市に移住し、横浜市都筑区の職場まで毎朝通っている。
ときおり日が差す薄曇りのある土曜日の朝、神奈川県三浦郡葉山町の大浜海岸で、ライフジャケットを身につけた子どもたち30人ほどの集団が浜辺をねり歩く。引率しているのは、もあなキッズ自然楽校のスタッフたち。そのうちの一人、上半身にウェットジャケットを着用した筋肉質で髭ぼうぼうの青年が、今回の主役、星野陽介さん。両側には低学年の子ども2人に手をつながれて、ゆっくりと歩を進める。
この日は、小磯の鼻と呼ばれる海に突き出した磯に繰り出して、主に潮溜まりで小魚やカニなどを捕まえたりする磯遊びグループと、水中メガネを着けてシュノーケルを咥えながら海面を泳ぐグループに分かれて、一日を過ごした。
星野さんは10名弱が手を挙げたシュノーケル班を率いて、波間をぷかぷかと浮かびながら泳ぎ進んでいった。
保育園や学童として子どもたちを受け入れ、週末を中心に湘南の海辺などでの野外体験活動を展開
NPO法人もあなキッズ自然楽校(以下、「もあな」)は、文字通り、子どもを対象に自然体験を提供する、いわゆる「自然学校」として2007年4月に設立したあと、2009年4月にNPO法人化した。事業理念として、「未来を創るのは子どもたちだ!」を掲げ、子どもたちの自然体験活動を通して、生きる力を育む環境と機会を提供するとともに、子どもが子どもらしく過ごすことのできる環境を守るための社会活動を展開することを事業内容としている。
特徴的なのは、法人の傘下に複数の保育施設を抱えるとともに、就学後の小学生たちにも学童保育や週末を中心とした野外体験プログラムを提供していること。
「もあなは、もともと自然体験活動を軸とした学校外教室を提供する放課後の居場所づくり事業からスタートしました。背景には、近年の子どもたちを取り巻く社会問題への危機感があって、子どもたちの健全な育成環境を取り戻そうというところが原点ですし、今も変わらず続けていることです。その後、横浜市都筑区のニュータウンで、地域のニーズに応じて近隣の保育施設と連携した“森のようちえん”スタイルの保育の充実化に関わるようになりました。森(自然)の中で保育をするというのに加えて、見守ることを大事にしながら、子どもたちとかかわっています」
“見守る”というのは、子ども一人ひとりの考えや主張を尊重し、保障することだと星野さんは話す。
例えば、冒頭で紹介した海辺の自然体験活動を例にとると、星野さんが担当するシュノーケルの活動をしたくないという子がいたとしても無理に強制することはない。磯遊びをしたい子は、一日中でも磯で遊んでいて構わない。
“やりたくない”にも何パターンかあると星野さんは言う。本当に海に入りたくない、いやだ!という子もいれば、入りたいけどちょっと怖いという子もいる。特に、まだ一度も体験したことがない子の場合、やりたい気持ちと不安がせめぎあっていることも容易に見て取れる。そんな時はそっと背中を押すように挑戦を促してみて、それでも「いや」という気持ちが強ければ、まだ機が熟していないとその子の選択を尊重する。あるいは、泳ぎたい気持ちもありながら、仲のいい子が磯遊びをするのに付き合って、今日は磯遊びを選択するという子もいる。同じ「やらない」の中にも、子どもたちそれぞれの理由が見え隠れする。ただそれも、子どもたちとの関係性が築けていれば、前後の様子や意思表示の仕方から、一人ひとりの選択の背景も見えてくる。
そんなふうに見守りながら、縁あって集まってきた子どもたちの信頼関係や人間関係の形成をめざす。 “仲間”としていっしょに遊び、活動して、人間のコアになる部分の豊かさを広げていくことを活動のメインにしている。
大浜海岸など海の活動を中心にした自然体験活動は、「海山キッズ」と称して年間10回の日帰り野外活動と、夏休み及び冬休みには3泊4日のキャンプを実施していて、毎月1回は顔を合わせることになる。
これまでは小学生までのプログラムだけだったが、昨年度から中学生向けのプログラムを始めた。法人ができて11年が経ち、初期に参加していた幼い子どもたちが、今はもう中学生以上になった。最初に参加した子は高校生になっている。幼い時代に感覚的に得た豊かな土壌を、さらに育んでいこうと、秋の連休に合わせて1泊2日のプログラムから始めている。
ピュアな人間同士のかかわりに魅力を感じた
星野さんにとって、もあなとの最初の出会いは、専門学校1年生のときにインターン実習生として、野外活動のスタッフを経験したことに遡る。いくつか受け入れ先があった中で、星野さんは第19回で紹介した同期の三瓶雄士郎さんとともに、もあなを実習先に選んだ。
インターン期間中のある日、江の島の近くでカヤックの活動があると言われて、三瓶さんと2人してフィールドに向かった。当時、カヤックは未経験だったため、活動が始まる前に、波がバシャバシャと押し寄せる磯辺で練習をすることになった。
「言われるままにカヤックに乗ってみたんですけど、とにかく初めてのことだったから、どうすればいいのかわからなくて、波に翻弄され、岸に打ち返されることの繰り返しでした。それでも、関山は黙って見ているだけ、しかもちょっと笑っているんですよ」
それまでもいろいろなところで自然体験や環境教育の活動の手伝いをしたりインターンに入ったりしたが、事前にきっちりと説明をしてくれるのが当たり前と思っていただけに、何も言わずに、ただ笑って見ているだけの関山さんの姿は衝撃的だった。
なんで助けてくれないの!というのがその瞬間の正直な気持ちだったが、あとあと落ち着いてから思い返すと、これだけ自由に、好きにやらせてくれるのって、実はすごいことなんだと思い至った。
こんな体験もあった。山の活動の手伝いに入ったとき、昼休みの自由に遊ぶ時間帯に、子どもたち5人ほどを引き連れて、ちょっとしたやぶ漕ぎをしながら探検隊ごっこをした。
「調子のいい子たちが、『隊長!』なんて呼んでくるので、自分も気分よくなって、『じゃあ行くぞ!』なんて言って歩き回っていたんです。ひとしきり遊んだ後、休憩場所に戻ってきて、出発の準備をしていたところに関山が寄ってきて、『今の、それがいいんだよ、それが!』としきりに言ってきたんですね。そのときはわけわからなくて、『あ、そうですか』と要領を得ない受け答えしかできなかったんですけど」
その日のプログラムが終わって、ふりかえりの席で話を聞くと、あんなふうにかかわりながら、思い入れの持てる共体験を重ねていくことが、子どもたちにとっても、星野さん自身にとっても、互いを受け入れ、関心を持つことにつながるんだという。それこそが人間関係を作っていくことにつながる。
専門学校の実習などでは高校生以上の大人を相手にしたインタープリテーションの方が多かったが、もあなでの実習を経て、変に壁を作ったり駆け引きをしたりすることなく、よりピュアな人間同士のかかわり方ができることに魅力を感じていた。
現在、もあなには、パート職員を入れて総勢70数名の職員が在籍しており、そのほとんどが保育資格を持つ。「自然楽校(学校)」という名前は付いていても、週末の野外活動のスタッフになりたいといって就職してくるような人は、星野さん以外には居ない。
星野さんは、平日には学童の担当スタッフとして子どもたちとかかわっている。学童といっても、学校の敷地内にあるわけではなく、保育施設があるセンター北周辺に「もあなのいえ」と名付けた施設を開設して、通える範囲のいろいろな学校から放課後に集まってくるという仕組みを取っている。あるいは、離れた学校に通っているものの、保育園に兄弟児がいる子が車で送迎してもらっているケースもある。
英語はしゃべれるようになったけど、英語がしゃべれる以外、何もできない
ここで少し、現在の職に就く前のことをさかのぼって、話を聞いた。
高校卒業後の進学先に、カナダの大学を選んだ。専攻はGeneral Studies(教養学)。学びたいことがカナダにあったというよりは、英語がしゃべれるようになりたいという思いからで、授業でも、英語に慣れることを優先して、カリキュラム内容以上に、ディスカッション形式など英語を聞いて話すことを優先した。例えば、「スピーチ」の授業や、造形で表現し説明をする美術系の授業などだ。
海外の大学に進学する将来設計を描いたのは、実は小学校4-5年の頃だった。
「自分は小さな頃から多趣味でした。将来やりたいことが見つかったときに、でもそれをできる環境が日本になかったとして、たかが言語の制約で可能性を閉ざされちゃいたくはないという思いがなぜかありました。日本語が通用するのって、日本国内だけじゃないですか。語学ができれば可能性が広がると思ったんですね」
カナダの大学と提携している高校の中学部があることを知って、中学受験をした。毎年何人か、カナダの大学に送り込んでいる学校だ。中学・高校時代をその学校で過ごして、大学進学を機に、提携しているカナダの大学に念願かなって入学できた。
ただ、3年間カナダで学んで帰国してきて、英語はしゃべれるようになったものの、社会に出て仕事をしようにも英語をしゃべることしかできないことに、ふと気づかされた。英語がしゃべれれば通訳になれるかというとそんなことはなく、自分よりも語学に堪能な人はいくらでもいるし、日本語力も必要な職業だ。今のままでは、自信を持って就ける仕事はない。だったら、専門学校に入るのが早道だろうと、いくつかあった候補の中から、自宅からでも通える東京環境工科専門学校を選んだ。カナダ留学の学資ローン返済と専門学校の学費を貯めるため、一年間のフリーター生活を経て、専門学校に入学したのは、2010年の春だった。
自然について学びたいと思うようになった背景には、カナダ時代に一年間ホームステイをした時の経験もあった。ホストファミリーに連れられて、カナディアンカヌーで何をするでもなくのんびりと川を下ってみたり、ハンティングやキャンプに連れて行ってもらったりした。乗馬をしながら3泊くらいキャンプをしたこともあった。それは特別な体験というわけではなく、現地の人たちにとってはごく普通のことで、日々の暮らしの中で自然とかかわることは、彼らにとって生活の一部だった。
カナダに行く以前にも、4歳くらいからボーイスカウトに入っていたことが、ふりかえって思うと今の仕事につながる最初のきっかけだったのかもしれない。大学時代はカナダにいたため活動に参加することはなかったが、籍は置いていた。帰国してまた関わるようになったが、その後、子どもの数が減っていき、別の団体と合併したのを機に活動から離れることになった。それでも、通算20年ほど活動してきた、大事な原体験だった。
自然とのかかわりはそんなふうにしてごく自然な形で育まれていったが、生涯にわたってやり続けていきたい、いわばライフワークとして捉えてきただけで、「仕事」にしたいという思いは、実はあまりなかった。もあなに出会って、自然体験を通して子どもの成長にかかれることに意義を感じるようになり、仕事としての意識を持つようになっていった。
雨が降っても濡れそぼっていた子が、自らレインウェアを着るようになる姿に人の成長を感じる
自然の中で遊ぶ子どもたちの姿を見ていて、“この子、自然で遊ぶのが好きなんだな”と感じられたときがもっとも手応えを感じると星野さんは言う。
保育園からもあなに通っていた子が小学生になってからも継続的に「海山キッズ」の活動に参加することももちろんあるが、小学生に入って初めて参加してくる子もいる。そんな子の中には、お昼の時間に地面に座ってお弁当を食べるよと言っても、地面に座ること自体ができないこともある。あるいは、雨が降ってきたのにレインウェアを自分で着ることもできないまま、どうしたらいいんだろうと立ちすくんで濡れそぼる子もいたりする。
そんなふうに基礎的な生活スキルが欠落したような子どもたちも、活動を参加し続けていくうちに、自然と雨が降れば自分でレインコートを出してきて着ているし、お弁当のときに手に砂がついても気にせずおにぎりを食べている姿を見ることもある。手を洗えばと言っても、いや、いいよと払うこともせずにいる。成長といってよいのかはわからないが、人って変わっていくものだと実感する出会いが日々訪れる。
「子どもと接していて困ることは、正直、ないんです。ただ、子どもたち本人との関係の背後には、家族との暮らしや学校生活などがあって、そうした子どもを取り巻く環境との兼ね合いで難しさを感じるところはあります」
もあなでは、子どもたち自身の思いや考えを大事にしたいし、優先させたいと思っているが、家庭には家庭の考えがあるし、学校には学校のやり方もある。ある子が、“困っているんだ”と言って悩みを打ち明けてきた。ところが話を聞いても、その子自身ではどうしようもないことだったりすると、「しょうがないよね」と慰めることしかできない場合もあって、もどかしさを感じる。
その逆に、学校など組織に属して枠にはめられることが当たり前になっていると、もあなの活動の中で自分自身を表現することが許されることに慣れていない子がオーバーリアクションで行き過ぎた行動を取ることもある。自由の中には責任がついてくるんだよと話しかけながら、人と人とのかかわりの中で生きていくことについて伝えるようにしている。
「実は、夢というか野望があって、いつか、環境教育を義務教育の中に入れたいと思っているんです。でも、自分1人が思っているだけでできることじゃないですよね。じゃあどうしたらいいかと考えたときに、実現できる人に同じような思いを持ってもらえばいいんじゃないか。それが教育であって、子どもを育てることなんだと思うんです。誰がそうなってくれるかはわかりませんけど、将来、そういうことができるようになる子がいたときのベースづくりをしていく、そんな思いで、今、子どもたちにかかわっています」
そのためにも、自然体験活動を重ねるとともに、自然や環境に対する知識も持ってほしい。もあなで仕事をするようになって、なんとなくわかってきたのが、「経験」というのは、「体験」と「知識」からなるものだということ。経験値を貯めるには、知識と体験の両方が必要になる。頭で理解をしていないと、体験だけでは追いつかないが、一方で、頭で理解するだけで体験が足りないと、実感に乏しくなる。
まずは自然に触れることが大事で、そこは義務教育としてすべての子どもたちがしっかりと体験してもらえたら、そこから先は興味も湧くだろうから、個人個人の意思で深めていけるようになる。
今年度の学童では、今地球で起きているプラスチック海洋汚染の問題について、極力客観的な事実として伝えてきたところ、子どもたちが自発的に近くを流れる川のごみ調査をはじめた。写真はその調査結果をまとめたもので、地域の祭りでポスター展示をして、子どもたちなりの思いをアピールした。
月1回の野外体験活動では伝えきれないことも、学童の子どもたちに対してなら、日々の活動で蓄積していきながら伝えられる。
ちなみに、ごみ調査で見つけたごみの中には、ビニールなどのプラスチックごみ以外にも廃棄自転車もあれば、回転寿司の皿まで捨ててあって、まるで社会の裏側を見たような表情で衝撃を受ける子どもたちだった。
自然楽校スタッフ・星野陽介さんの“七つ道具”
- ナイフ…土佐のお土産でもらったクジラをかたどったナイフ。1枚の金属板からできている丈夫なもので、雑に扱っても気にせず使えるのがお気に入り。自然体験活動ではもちろん、学童で木工をするときにも慣れたこのナイフを使うことが多い。
- ポンチョ…本来の使用目的である雨具や防寒具としてはリュックを背負ったまま被れるので重宝する。それ以外にも、広げればシートになるし、木に縛ってタープのように張って日除けにもなるという万能品。ソロキャンプに行くとき、テントを持っていかずにハンモックだけリュックに入れて、タープ代わりに張って雨露をしのいで寝ることも多い。
- 万年筆…真鍮製。長く使えるものがほしいと思って探していたときに出会って、一目惚れした逸品。革クラフトが好きなので、ケースは自作した。
- 水筒
- 名刺入れ
- ヘッドライト…アウトドア仲間の結婚式の引き出物としてもらったもの。常に携行している。
- 手帳…薄い木にプラスチック板を裏地にして補強した、自作品。予定を書き込むのはもちろん、フィールドノートのように野外で立ったまま書きこむため、表紙を固くしたこだわりの一品だ。
一日の“タイムスケジュール”
平日編
| 7時 | 起床 |
| 8時 | 平塚の自宅を出発すれば、9時半-10時頃に横浜市の職場に到着 午前中は事務作業や打ち合わせなどで時間が過ぎていく |
| 12時-13時 | 昼休み |
| 14時頃- | 学校の授業を終えた子どもたちが順次学童にやってくる。施設内で中遊びをしたり、公園など外遊びに出かけたりする。外遊びの行き先は子どもだけで決めている。時に高学年の子どもたちの発言力が強すぎて低学年の子が抑えられてしまう場合には手助けもするが、基本的には子どもたちに任せて決めさせ、大人スタッフは引率に徹している。 室内遊びを好む子もいる。チラシを細長く丸めて剣を作ったり、木片を組み合わせて鉄砲のようなものを作って遊んだりする子もいる。折り紙や塗り絵をしたり、あるいは宿題に取り掛かったりする子もいる。高学年の子が「今日は宿題をやらないと!」と言って広げていると、小さい子たちも真似してノートを開いたりする。 畑作業もしている。NPO法人で借りている畑の一区画を学童でも使っている。栽培する野菜も子どもたちの思いを汲み取って決めている。家では食べない野菜でも、自分たちの育てた野菜はむしゃむしゃ食べる。 |
| 18時頃 | お迎えの時間までには施設に戻るようにする。言わないとひたすら遊んでいる子どもたちだ。 迎えに来る保護者には学童中の様子を伝えたり、逆に普段と様子が違う子がいたら、学校や家庭での様子を聞いたりして、コミュニケーションを取っている。 |
| 19時頃 | 子どもたちが帰った後に学童を閉めて、帰宅の途に着く。 |
| 20時半-21時 | 帰宅後は、晩酌しながら奥さんとの時間を過ごして、ゆっくりする。 |
| 23時-24時頃 | 就寝。 |
週末の野外体験編
| 4時 | 起床 |
| 4時半 | 自宅発。平塚の自宅からは湘南の海の方が近いが、いったん横浜市の職場まで出勤する。 |
| 7時前 | 到着後、当日の最終的な出欠状況を確認し、持っていく荷物の準備などを始める。 7時半になると、他のスタッフも到着してくる。全員揃ったところで、最終確認のスタッフミーティング。 |
| 8時 | 参加者の子どもたちは横浜市営地下鉄のセンター北駅に集合してくるので、駅で受け付けをする。 送迎の保護者たちにその日の活動を伝えて別れたあと、現地まで電車とバスを乗り継いで、移動。 |
| 10時頃 | 現地到着。子どもたちにはその日の予定や活動の注意点を伝え、初めての子がいる場合にはアイスブレークをしながら、ゆっくりスタートする。 |
| 12時- | 昼休み。何もしない自由に遊べる時間も大事にしている。 |
| 13時- | 午後のプログラム開始。午前中とやることを変えてもよい。もちろん、一日同じことをして遊ぶのもOKだ。 |
| 15時頃 | 場所によって時間のズレはあるものの、活動を終了して、着替えなど帰路につく準備をする。 |
| 17時頃 | もあなに帰還。帰りのお迎えは施設で受け付ける。お迎えが来るまでの間、毎回必ず活動のふりかえりをして、その後、遊んで過ごす。お迎えに来た保護者には、その日の様子を伝えたりして、共有。保育園時代から通っている世帯など、何年も参加している子も多いから、親兄弟など本人以外の話で盛り上がることもある。 |
| 18時半頃 | 子どもたちが全員帰ったあと、スタッフだけで活動のふりかえりをする。1時間ほどで終了。 そのまま家に帰ることもあれば、ちょっと話足りないときにはラーメン屋などに行って話し込む。 |
| 21時頃 | 帰宅後は、晩酌しながら、奥さんとの時間を過ごす。 |
休日は、平塚周辺に限らず、相模湾で遊ぶことが多い。野外活動で訪れるところに遊びに行くことも多い。
カヤックを持っていったり、釣りをしたり、暖かくなってきたらシュノーケルをしたりする。台風が近づいてきて、波が高くなった時にはサーフィンを楽しむなど、海遊びをすることが多い。
このほか、夏のキャンプのフィールドにしている西伊豆へ、視察や打ち合わせと遊びを兼ねて出かけることもある。
関連リンク
バックナンバー
- 001「身近にある自然の魅力や大切さをひとりでも多くの人に伝えたい」 -インタープリター・工藤朝子さん-
- 002「人間と生き物が共に暮らせるまちづくりを都会から広げていきたい」 -ビオトープ管理士・三森典彰さん-
- 003「生きものの現状を明らかにする調査は、自然を守るための第一歩」 -野生生物調査員・桑原健さん-
- 004「“流域”という視点から、人と川との関係を考える」 -NPO法人職員・阿部裕治さん-
- 005「日本の森林を守り育てるために、今できること」 -森林組合 技能職員・千葉孝之さん-
- 006「人間の営みの犠牲になっている野生動物にも目を向けてほしい」 -NPO法人職員・鈴木麻衣さん-
- 007「自然を守るには、身近な生活の環境やスタイルを変えていく必要がある」 -資源リサイクル業 椎名亮太さん&増田哲朗さん-
- 008「“個”の犠牲の上に、“多”を選択」 -野生動物調査員 兼 GISオペレーター 杉江俊和さん-
- 009「ゼネラリストのスペシャリストをめざして」 -ランドスケープ・プランナー(建設コンサルタント)亀山明子さん-
- 010「もっとも身近な自然である公園で、自然を守りながら利用できるような設計を模索していく」 -野生生物調査・設計士 甲山隆之さん-
- 011「生物多様性を軸にした科学的管理と、多様な主体による意志決定を求めて」 -自然保護団体職員 出島誠一さん-
- 012「感動やショックが訪れた瞬間に起こる化学変化が、人を変える力になる」 -自然学校・チーフインタープリター 小野比呂志さん-
- 013「生き物と触れ合う実体験を持てなかったことが苦手意識を生んでいるのなら、知って・触って・感じてもらうことが克服のキーになる」 -ビジターセンター職員・須田淳さん(一般財団法人自然公園財団箱根支部主任)-
- 014「自分の進みたい道と少しかけ離れているようなことでも、こだわらずにやってみれば、その経験が後々活きてくることがある」 -リハビリテーター・吉田勇磯さん-
- 015「人の営みによって形づくられた里山公園で、地域の自然や文化を伝える」 -ビジターセンター職員・村上蕗子さん-
- 016「学生の頃に抱いた“自然の素晴らしさを伝えたい”という夢は叶い、この先はより大きなくくりの夢を描いていくタイミングにきている」 -NPO法人職員・小河原孝恵さん-
- 017「見えないことを伝え、ともに環境を守るための方法を見出すのが、都会でできる環境教育」 -コミュニケーター・神﨑美由紀さん-
- 018「木を伐り、チップ堆肥を作って自然に返す」 -造園業・菊地優太さん-
- 019「地域の人たちの力を借りながら一から作り上げる自然学校で日々奮闘」 -インタープリター・三瓶雄士郎さん-
- 020「もっとも身近な、ごみの処理から環境に取り組む」 -焼却処理施設技術者・宮田一歩さん-
- 021「野生動物を守るため、人にアプローチする仕事を選ぶ」 -獣害対策ファシリテーター・石田陽子さん-
- 022「よい・悪いだけでは切り分けられない“間”の大切さを受け入れる心の器は、幼少期の自然体験によって育まれる」 -カキ・ホタテ養殖業&NPO法人副理事長・畠山信さん-
- 023「とことん遊びを追及しているからこそ、自信をもって製品をおすすめすることができる」 -アウトドアウェアメーカー職員・加藤秀俊さん-
- 024「それぞれの目的をもった公園利用者に、少しでも自然に対する思いを広げ、かかわりを深くするためのきっかけづくりをめざす」 -公園スタッフ・中西七緒子さん-
- 025「一日中歩きながら網を振って捕まえた虫の種類を見ると、その土地の環境が浮かび上がってくる」 -自然環境コンサルタント・小須田修平さん-
- 026「昆虫を飼育するうえで、どんな場所に棲んでいて、どんな生活をしているか、現地での様子を見るのはすごく大事」 -昆虫飼育員兼インタープリター・腰塚祐介さん-
- 027「生まれ育った土地への愛着は、たとえ一時、故郷を離れても、ふと気付いたときに、戻りたいと思う気持ちを心の中に残していく」 -地域の森林と文化を守るNPO法人スタッフ・大石淳平さん-
- 028「生きものの魅力とともに、生きものに関わる人たちの思いと熱量を伝えるために」 -番組制作ディレクター・余座まりんさん-
- 029「今の時代、“やり方次第”で自然ガイドとして暮らしていくことができると確信している」 -自然感察ガイド・藤江昌代さん-
- 030「子ども一人一人の考えや主張を尊重・保障する、“見守り”を大事に」-自然学校スタッフ・星野陽介さん-
- 031「“自然体験の入り口”としての存在感を際立たせるために一人一人のお客様と日々向き合う」 -ホテルマン・井上晃一さん-
- 032「図面上の数値を追うだけではわからないことが、現場を見ることで浮かび上がってくる」 -森林調査員・山本拓也さん-
- 033「人の社会の中で仕事をする以上、人とかかわることに向き合っていくことを避けては通れない」 -ネイチャーガイド・山部茜さん-
- 034「知っている植物が増えて、普段見ていた景色が変わっていくのを実感」 -植物調査員・江口哲平さん-
- 035「日本全国の多彩なフィールドの管理経営を担う」 -国家公務員(林野庁治山技術官)・小檜山諒さん-
- 036「身近にいる生き物との出会いや触れ合いの機会を提供するための施設管理」 -自然観察の森・解説員 木谷昌史さん-
- 037「“里山は学びの原点!” 自然とともにある里山の暮らしにこそ、未来へ受け継ぐヒントがある」 -地域づくりNPOの理事・スタッフ 松川菜々子さん-
- 038「一方的な対策提案ではなく、住民自身が自分に合った対策を選択できるように対話を重ねて判断材料を整理する」 -鳥獣被害対策コーディネーター・堀部良太さん-
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.