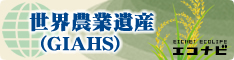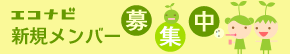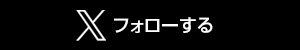- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 食べる
- 世界農業遺産(GIAHS)
- 039 韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催
0392025.10.14UP韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催
9月18日から20日まで韓国の済州島で第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)が開催され、日中韓の農業遺産関係者約250名が参加し、交流を深めました。また、これに先立ち、9月5日には中国福建省福州市で第2回お茶関係農業遺産シンポジウム、9月12日~13日には中国湖南省新化県で第9回農業文化遺産会議がそれぞれ開催されました。
今回は、第9回東アジア農業遺産学会を中心に、最近の農業遺産をめぐる動きについて紹介します。
韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)を開催
9月18日から20日まで韓国の済州島で第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)が「農業遺産の持続的な保全とコミュニティの回復」をテーマに開催され、日中韓やFAOの農業遺産関係者約250名が参加し、交流を深めました。日本からは農林水産省農村環境対策室の吉見友弘室長をはじめ農業遺産認定地域の関係者、大学の研究者ら約40名、中国からも約40名が参加しました。
東アジア農業遺産学会(ERAHS)の背景と経緯についてはエコレポ33号で紹介しましたが、複雑な日中・日韓関係の下でアカデミックな交流から始まったERAHSにおいて、先般の日中韓農業大臣会合共同声明を受けてポリシー(政策)トラックの交流も始まったのが、今回のERAHSの大きな特徴です。
開催地の済州島には、「済州島の石垣農業システム」(2014年認定)と「済州の海女漁業システム」(2023年認定)の2つの世界農業遺産があります。「済州島の石垣農業システム」は、火山島特有の強風と石だらけの畑という厳しい環境の中で、農民は畑の土の中の石を積み上げて畑を囲み、風を防ぎ作物を守ってきました。この黒い石垣は農業にとって重要であるばかりでなく、景観的にも優れ、観光面でも利用されています。また「済州の海女漁業システム」は、素潜りでアワビやサザエ、海藻などを採る済州島の海女が、かつては島の女性人口の2割以上を占めるほど重要な位置づけにあり、持続的な漁業を通じて海と調和した生活を営んできました。
また、済州島は中国からの参加者にとって、日本や韓国を訪問するのには必要なビザの取得が要らないという利点があります。
第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)の概要
9月18日に会場の済州オリエンタルホテルで開催された開会式では、韓国農村遺産学会会長による主催者挨拶、済州特別自治道知事と国会議員による歓迎挨拶、FAO韓国事務所代表、韓国農林畜産食品部、韓国海洋水産部による祝辞に続き、海女によるパフォーマンスがありました。
続く基調講演では、FAOのジェレミー・ムバイラマジ上級コーディネーター(GIAHS事務局長)が「GIAHSのグローバルな概観:成果、課題、そして今後の展望」と題して、現在のGIAHSの全体像を説明し、ERAHS名誉議長の武内和彦教授が「地球環境時代における農業遺産の意義」と題して、気候変動や生物多様性の相互関係、自然資源を生かした能登の震災復興、食料やウェルビーイングにおけるGIAHSの意義を強調しました。 また、中国ERAHS議長のミン・チンウェン教授と韓国ERAHS議長のユン・ウォングン教授は、それぞれ中国と韓国の農業遺産の現状を紹介しました。
その後、4つの分科会に分かれ、発表が行われました。分科会のテーマは、①生態系サービスと農業遺産サイトでの保全、②農業遺産産品の認証・ブランド化・プロモーション、③3か国間での農業遺産政策の比較分析、④持続的な農業遺産ツーリズムと事例で、ナビゲーターはセッション2のモデレーターを務めるとともに、セッション3で「中国、韓国と比較した日本の農業遺産」について発表しました。日中韓の農業遺産制度の比較分析は、ナビゲーターが以前から取り組んでいる研究テーマであり、この3か国の農業遺産制度には多くの共通点がありながら、それぞれの国情を反映した違いも少なくなく、興味深いところです。例えば、農業遺産の評価に関して、日本はアクション・プラン(保全計画)に基づく評価、韓国は補助事業の効果に重点を置いた評価、中国は客観的な指標に基づく評価といった違いがあります。
分科会終了後には、ERAHSで初めて公式な「中央政府会議」が開催されました。これは先般の日中韓農業大臣会合共同声明を受けて開催されたもので、3か国の中央政府間における農業遺産関連の今後の協力について友好的な雰囲気の中で議論が交わされ、今後もERAHSの場を活用してこの会議を継続的に開催していくことなどが合意されました。
翌9月19日は、午前中に各国の政府代表による基調発表が行われ、日本からは農林水産省農村環境対策室の吉見友弘室長が「日本における世界農業遺産・日本農業遺産の取組」について発表されました。続いて、残り2つの分科会、⑤若い世代と多様なステークホルダーの参加、⑥漁業遺産の保全管理の発表があり、その後、各分科会のモデレーターがそれぞれ分科会の概要を報告し、最後に閉会式が行われました。
閉会式では、次回開催予定地の中国湖南省新化県(「中国の南部山岳丘陵地域における棚田システム」(2018年認定))から、紫鵲界(しじゃくかい)棚田の紹介とともに、2026年9月18-21日に第10回ERAHS会合を開催するという発表がありました。
午後は、各国ごとにバスに分乗してエクスカーション(現地調査)に出かけ、済州童話村、済州石公園、セファ村(地域振興プロジェクト)、海女博物館を訪問しました。
翌9月20日の午前中にERAHS作業会合が開催され、今回の評価と次回の計画が話し合われました。ナビゲーターからは、今回のERAHS会合は、①夜の交流会が充実していて参加者のコミュニケーションがよく図られたこと、②初めて採用されたAI通訳は最初とまどいがあったものの慣れると実用的にそれほど大きな問題は感じなかったこと、③エクスカーションでは実際の畑などの現場をもっと見たかったことなどを発言しました。また、3か国で共通のERAHSのウェブサイトを設けることなどを提案しました。
中国福建省福州市で第2回お茶関係農業遺産シンポジウムを開催
9月5日には中国福建省福州市で第2回お茶関係農業遺産シンポジウムが開催され、日本からナビゲーターが参加しました。実は、静岡県の世界農業遺産「静岡の茶草場農法」地域が招待を受けたのですが、いろいろと手違いがあって代表派遣が間に合わず、同推進協議会のアドバイザーを務めているナビゲーターがピンチヒッターとして参加したということです。
このシンポジウムは、昨年12月に開催された第1回に続くもので、日本と韓国の代表、中国の15の農業遺産地域の代表を含め約50名が参加しました。中国語では「茶類農業文化遺産連盟第2回工作会議」といいますが、この「連盟」(Alliance)は日本の「農業遺産認定地域連携会議」のようなもので、お茶に関係する農業遺産地域等が情報交流するためのプラットフォームです。ただ、事務局は日本の連携会議のような持ち回りではなく、福州市で固定されています。
シンポジウムでは、「連盟主席」(福州市副市長)の挨拶に続いて、各認定地域から5分程度の報告が行われ、ナビゲーターは、静岡の茶草場の紹介、保全活動の重要性、日中韓が協力してお茶に関する農業遺産を次世代に継承していくことなどを、上手ではありませんが中国語でスピーチしました。
なお、今回のシンポジウムには、お茶の農業遺産地だけでなく、稲作や棚田、淡水養殖の農業遺産地域も参加しており、「融合」を重視して、このような農業遺産地域にもお茶を広めていくのだという説明でした。
日本と韓国からの招待は、このシンポジウムの格を国際的なものに高めるためと思われ、全行程に専任の日本語通訳をつけていただくなど、来賓として大変丁重な接遇を受けました。
シンポジウム以外の行事としては、9月5日(金)の午前に「第五届福州茉莉花茶文化节和第四届福州茶叶交易会」(第5回福州ジャスミン茶文化祭及び第4回福州茶葉見本市)の開幕式への出席、9月6日(土)の午前に「五里亭茶城」というお茶関係の店舗が集積したビルの見学を行い、午後にはジャスミン茶の利き茶コンテストに参加しました。
中国では、習近平主席の発言が非常に重視されており、お茶に関しては、2021年に習近平主席が福州市を視察した際に茶文化、茶産業、茶の科学技術を総合的に発展させる「三茶」を強調したこと、農業遺産に関しては、2022年に浙江省の青田県で開催された世界農業遺産大会への祝辞において、農業文化遺産の保護と利用、経済・社会・文化・環境・科学技術面における価値を強調したことが常に話題に上がっていました。
本シンポジウムは、先般の日中韓農業大臣会合共同声明で提案された日中韓の農業遺産の協力の一つのモデルにもなり得るものと思います。
中国湖南省新化県で第9回農業遺産文化会議を開催
9月14~15日に中国湖南省新化県で国際機関の来賓、政府関係者、専門家、大学院生など約4百人が参加して、「2025紫鵲界棚田と世界との対話」をテーマに、第3回農耕文化交流学習大会及び第9回農業遺産文化会議が開催されました。ナビゲーターは、開幕式後の基調講演を行うために昨年に続いて今年も招待を受けました。
実は、この新化県は前述のとおり来年のERAHSの開催予定地であり、今回の訪問はその下見の意味もありました。広大な国土を有する中国では、世界農業遺産の多くは遠隔地にあるのですが、ここもその例外ではなく、一番近い長沙(ちょうさ)空港からでも約3時間かかります。成田空港から長沙空港までは直行便があるのですが、火曜日と金曜日にしか飛んでおらず、今回は金曜日のイベントで木曜日中には到着している必要があったので、結局、上海で1泊して、上海虹橋駅から新化南駅まで高速鉄道(新幹線)で7時間かけて移動しました。
この経験から、来年のERAHSは金曜日の直行便を利用できるように、土曜日から始まるよう日程を設定してもらいました。ERAHSを平日に開催するか、週末に開催するかは意見の分かれるところで、県の方など本来業務としてERAHSに参加される方は平日を、平日に授業のある大学の先生など農業遺産を本来業務とされていない方は週末の開催を希望されます。今回は後者を優先させていただき、5連休を利用して、金曜日以外は休日を利用できるようにしてもらいました。
さて話を戻して、この紫鵲界の棚田は、2018年に世界農業遺産に認定された「中国の南部山岳丘陵地域における棚田システム」の一部です。システム全体は、湖南省・江西省・広西チワン族自治区などに広がる伝統的な水稲農業の地域で、漢族や瑤族、苗族など多様な民族が、山の斜面を利用して水源を巧みに管理し、自然と共生する形で稲作を続けています。その中でも紫鵲界棚田は代表的なエリアで、標高差数百メートルにわたり約3300ヘクタールの棚田が連なっています。独特の水管理技術や輪作体系、民族文化と景観が一体となっており、街に近い一部が観光地化されて、入場料をとって公開されています。
今回は時間がなくて入り口部分のごく一部しか見られませんでしたが、来年はもっと奥まで行ってみたいと思っています。
バックナンバー
- 001「世界農業遺産とは?」
- 002「新潟県佐渡市で第2回東アジア農業遺産学会を開催」
- 003「先進国で初めて認定された、日本の世界農業遺産」
- 004「世界農業遺産に日本の新しい3地域が認定」
- 005「世界農業遺産認定の活用とその成果」
- 006「世界農業遺産のモニタリングと評価」
- 007「世界農業遺産の新たな進展」
- 008「日本農業遺産の初めての認定」
- 009「日本農業遺産の認定地域の紹介」
- 010「中国湖州市で第4回東アジア農業遺産学会を開催」
- 011「宮城県大崎地域が日本で九番目の世界農業遺産に認定」
- 012「静岡県わさび栽培地域と徳島県にし阿波地域が世界農業遺産に認定」
- 013「和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会を開催」
- 014「3地域が世界農業遺産の申請を承認、7地域が新たに日本農業遺産に認定」
- 015「韓国ハドン郡で第6回東アジア農業遺産学会を開催」
- 016「日本の3地域がFAOへ世界農業遺産の認定を申請」
- 017「農林水産省が世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域の募集を開始」
- 018「12地域が世界農業遺産・日本農業遺産の一次審査を通過」
- 019「コロナ禍の中での世界農業遺産」
- 020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」
- 021「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(後編)」
- 022「初の認定から10年が経過し、新たな展開が期待される日本の世界農業遺産」
- 023「石川県能登地域で「世界農業遺産国際会議2021」を開催」
- 024「農林水産省は世界農業遺産・日本農業遺産の認定等を希望する地域を募集中」
- 025「山梨県峡東地域と滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定」
- 026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」
- 027「4年ぶりに東アジア農業遺産学会を中国の現地で開催へ」
- 028「中国慶元県で第7回東アジア農業遺産学会を開催」
- 029「兵庫県兵庫美方地域と埼玉県武蔵野地域が新たに世界農業遺産に認定」
- 030「国内外の各地で世界農業遺産認定後の記念イベントを開催」
- 031「アンドラ、オーストリア、中国、イラン、韓国の8地域が新たに世界農業遺産に認定」
- 032「国連大学OUIKが能登復興支援シンポジウムを開催」
- 033「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」
- 034「オーストリア、インドネシア、サントメ・プリンシペの3地域が世界農業遺産に認定」
- 035「新たに4地域が日本農業遺産に認定」
- 036「今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定」
- 037「ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定」
- 038「島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定」
- 039「韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.