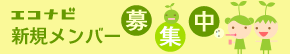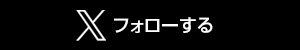- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 集まる
- ミュージアムグッズを入り口に
- 016 【東京農工大学科学博物館】カイコ研究に触れられる「カイコのマスキングテープ」 貴重!カイコのマスキングテープ
エコレポトップページへ
ミュージアムグッズを入り口に
0162025.08.13UP【東京農工大学科学博物館】カイコ研究に触れられる「カイコのマスキングテープ」 貴重!カイコのマスキングテープ
東京農工大学科学博物館の新しいミュージアムグッズとして、カイコのマスキングテープが販売されたとのこと。筆者はカイコが大好きで、かつて勤務していた会社でカイコを飼育していました。幼虫のすべすべとした滑らかな肌を撫でることで、仕事の疲れを癒していたものです。
マスキングテープは全2種。緑色の「カイコのイラスト」柄では、カイコの飼育の流れがイラストで紹介されており、幼虫・成虫・繭・桑の葉が描かれています。日本在来種の蚕「小石丸」の3齢幼虫を参考にしているそうで、丸々とした姿がとてもかわいらしいです。
注目すべきもう一つの柄は、「カイコのCOI遺伝子」です。カイコの遺伝子の中でも、COI遺伝子の配列を中心にデザインされています。COI遺伝子とは、ミトコンドリアDNAに含まれる遺伝子のひとつ。動物ならほぼすべての種がこの遺伝子を持っているため、種の同定などに使いやすく、現在のDNA分析に多用されているそうです。
カイコの遺伝子配列がデザインされたマスキングテープなんてミュージアムショップでしか買えませんし、研究で取り組んでいる内容が反映されているのも大学博物館ならではですよね。
カイコの「研究」ってなんだろう
東京農工大学農学部には蚕学研究室があります。蚕学…という分野を初めて知りました。どのような学問なのでしょうか。
そもそも生物生産を担う農業は大きく分けて、野菜や果物を育てる「植物生産」と、牛や豚などの動物を育てる「動物生産」に分類されます。農業の一分野である養蚕はカイコという動物を育てるため「動物生産」に関わる一方で、エサとなる桑を育てるため「植物生産」にも関わるという、少し特別な分野なのです。
農業について教育研究する学問の中には、稲や麦を研究する作物学や、野菜や果物を研究する園芸学、動物を研究する畜産学など色々な分野がありますが、その中の一つにカイコの飼育等を中心とした養蚕学があって、農学の中で確たる位置を占めています。
蚕学はカイコの身体や生命について研究する学問で、養蚕学や、エサとなる桑の木の栽培技術を教育研究する栽桑学、蚕の繭からとれる生糸に関連した製糸学や蚕糸業経営学など、養蚕が盛んだった時代に主に産業的観点から発展してきた学問分野が時代の変遷とともに役割を変えていく過程で、東京農工大学では「蚕学」へと改組・改称されていったのです。
前身の養蚕学などの研究成果は、良質な繭をたくさん生産するための品種改良や飼育方法の工夫など、カイコの飼育技術の向上に大きく貢献してきた他、生き物の遺伝の仕組みや、カイコの体が作られるプロセス(発生)や体の働き(生理)などをテーマとする基礎研究でも重要な役割を果たしており、さらに今後より幅広い分野への活用が期待されます。
繊維業界では人工繊維の製造に高いエネルギーを消費することが課題の一つになっています。カイコは、常温下で強い繊維を口から吐き出して作っていますから、そんな環境負荷の少ない繊維製造方法が人工繊維でも実現すればなんてことも古くから取り組まれています。
カイコ研究にまつわる資料
カイコに関する教育や研究の基礎となるのは、カイコの遺伝学です。カイコの体の形成過程や機能に関する研究も、遺伝学の知識によって大きく発展してきました。東京農工大学農学部の蚕学研究室では、40年以上にわたり、カイコの発生遺伝学や生理遺伝学の教育と研究が行われてきました。
こうした研究成果は、東京農工大学科学博物館のミュージアムグッズの中にも生かされています。
「紙製クリアファイル1(蚕模型〈微粒子病〉)」も印象的なアイテムのひとつです。クリアファイルには、微粒子病というカイコの幼虫がかかる病気の様子を再現した模型が描かれています。これもまた、カイコに関する研究と教育の歴史が受け継がれてきたことを物語る、貴重な資料のひとつです。このように、研究の一端に触れられることも、ミュージアムグッズの大きな魅力といえるでしょう。
ミュージアムグッズは博物館を思い出すきっかけにもなります。蚕が吐き出す生糸とそれを紡いでできる絹の製造工程や紡績機械などを思い出しつつ、自宅でタンスの肥やしになっているお気に入りだった衣服(もしあれば)やシーズンごとに彩りを変えるファッションブランド店に並ぶ衣類の数々など、絹産業がめざした繁栄の結果と今日の人類のくらしに思いをはせてみてもよいかもしれません。
参考HP
バックナンバー
- 001「ミュージアムグッズは博物館の使命への誘い」
- 002「【鳥羽市立 海の博物館】海と生きる姿を描いた「海女さんメモロール」」
- 003「【京都水族館】実物を観察しているみたい「オオサンショウウオぬいぐるみ」」
- 004「【知床羅臼ビジターセンター】野生動物のきらめきを手に「シレトコ野帳」」
- 005「【奥州市牛の博物館】牛のこと、牛と私たちのこと「牛品種手ぬぐい」」
- 006「【明治の森高尾国定公園 東京都高尾ビジターセンター】ビジターセンターの発信とオリジナルグッズの役割「山のお宝シリーズ【ピンバッチ】」」
- 007「【那須どうぶつ王国】ライチョウが愛おしくなるクッキー「雷鳥クッキー」」
- 008「【竹中大工道具館】道具を残し、職人技を伝える「キーホルダー」」
- 009「【PLAY! PARK】キラキラの思い出をいつまでも「FRAME BAG」」
- 010「【中山道広重美術館】ある旅の日の、江戸時代のあなたへ」 -「広重おじさんトランプカード〈東海道五十三次〉」-
- 011「【松戸市立博物館】歴史は遠い日の過去ではない「2DKの住まい(マスキングテープ)」」
- 012「【熊本市現代美術館】災害から動物園を守るために「絵本『どうぶつたちもこわかった』」」
- 013「【札幌市円山動物園】ノートの見返しはウンチペーパー!「ZOOTE」」
- 014「【足立区生物園】自然と学びにつながる「蓄光で光る!ホタルトートバッグ」」
- 015「【石川県西田幾多郎記念哲学館】哲学を学べるミュージアムの「哲学者ふせん」」
- 016「【東京農工大学科学博物館】カイコ研究に触れられる「カイコのマスキングテープ」 貴重!カイコのマスキングテープ」
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.