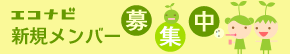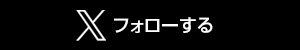メインコンテンツ ここから
- HOME
- 連載コラム「エコレポ」
- 学ぶ
- レポート一覧
エコレポトップページへ
エコライフ連載コラム「エコレポ」バックナンバー
「学ぶ」のレポート一覧
総件数:123件 PAGE 10/13 前へ 8 9 10 11 12 次へ

- ジャンル:学ぶ
- 自分の進みたい道と少しかけ離れているようなことでも、こだわらずにやってみれば、その経験が後々活きてくることがある
- 2013.12.03UP [自然を守る仕事 014]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 事故などに遭って怪我をした野生動物の治療後のケアや野生復帰に向けた訓練などを行うリハビリテーターという職業がある。いわば野生動物を野生に復帰させるためのケアを実践する仕事である。中でも、野生状態のものは日本では北海道でしか見られないオオワシ・オジロワシやシマフクロウなどの希少猛禽類を専門に扱っているのが、環境省釧路湿原野生生物保護センターを拠点とする猛禽類医学研究所。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 生き物と触れ合う実体験を持てなかったことが苦手意識を生んでいるのなら、知って・触って・感じてもらうことが克服のキーになる
- 2013.10.01UP [自然を守る仕事 013]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - “天下の険”と謳われる箱根の山。山の上で湖水を湛える芦ノ湖畔に建つ「箱根ビジターセンター」が、今回の主人公・須田淳さんの職場。同センターは、富士箱根伊豆国立公園・箱根地域を訪れる人たちに、公園内の自然情報をわかりやすく展示・解説し、箱根を散策する際の出発点になることを目的とした拠点施設だ。ビジターセンターを運営する自然公園財団箱根支部では、この他、箱根地域の調査研究とそれを踏まえた保全活動(例えば、オオハンゴソウなどの外来生物の駆除や、希少動植物の保護活動など)や普及啓発、また観察会やハイキングイベントなどの企画・運営、100名近くいるパークボランティアの活動支援など、多岐にわたる業務を9人いるスタッフで担っている。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 児童書の世界を楽しむ、ものがたりライブとおもちゃの話
- 2013.08.27UP [本やウェブでエコを知る 002]
 エコナビ 編集部
エコナビ 編集部 - この夏、小淵沢の「なぞなぞ工房」を訪れた。『用寛さん』『青空晴之助』などの子供講談シリーズや『あなたも名探偵』シリーズといった児童書作家として知られ、近年はストーリーテラーとして活躍の場を広げている杉山亮さんの自宅書斎で開催する「ものがたりライブ」に参加するためだ。8月1日から31日までのほぼ毎日、午後1時および午後2時半に開始する1回約40分のトークイベント。うち11日間は、夜8時から始まる「夏のおばけ話ライブ」も実施されている。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 感動やショックが訪れた瞬間に起こる化学変化が、人を変える力になる
- 2013.06.04UP [自然を守る仕事 012]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 富士山の西麓、柚野という美しい里山に30年の歴史を持つ「ホールアース自然学校」の富士山本校がある。『1人1人が「人・自然・地域が共生する暮らし」の実践を通じて、感謝の気持ちと誇りをもって生きている。』そんな社会を目指して、約40名のスタッフが活動する老舗の自然学校である。その富士山本校から車で30分。富士山の真西に位置する、知る人ぞ知る湖「田貫湖」。この地に環境省が進める自然学校の第1号として2000年7月に開設した「田貫湖ふれあい自然塾」がある。2階建ての自然体験ハウスを中心に、さまざまな遊びや学びが体験できる施設だ。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 生物多様性を軸にした科学的管理と、多様な主体による意志決定を求めて
- 2013.01.29UP [自然を守る仕事 011]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 日本自然保護協会(通称NACS-J)は、日本の自然環境系NGOの草分けとして知られる。開発による自然環境破壊や影響を回避したり軽減したりするための運動や政策提言、そのベースになる調査・研究、また地域や日本社会全体の理解や世論を高めることにつながる環境教育の取り組みなど、多岐に渡る活動を古くから続けてきた日本屈指の老舗自然保護団体の一つだ。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- もっとも身近な自然である公園で、自然を守りながら利用できるような設計を模索していく
- 2012.11.13UP [自然を守る仕事 010]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 前回紹介した亀山明子さんと同じ(株)ランズ設計研究所に務める甲山隆之さんは、野生生物調査を専門にしている。元は植物が専門だったが、今や猛禽類や昆虫など生き物全般の調査業務に携わる。同社は主に都市公園の計画づくりを行う建設コンサルタント会社だが、職務内容によって大きく分類すると、公園等の設計方針や計画内容を決める「計画班」と、計画に基づいて図面を引いたりする「設計班」の2つに分けられる。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- ゼネラリストのスペシャリストをめざして
- 2012.10.02UP [自然を守る仕事 009]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 近年、行政の計画づくりや意思決定の場面で、施策の対象である地域住民の意見や意向を幅広く求める情報交換や意思形成のプロセスが重視されている。いわゆる住民参加の計画づくりだ。公園づくりでも、新設公園はもちろん既設公園の再整備などにおける整備方針や計画の策定プロセスで、いかに地域の関係団体や住民の意見や意向を反映させるか工夫を凝らすケースが多くなっている。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- “個”の犠牲の上に、“多”を選択
- 2012.07.17UP [自然を守る仕事 008]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 「野生動物の調査は、食痕や糞などを探しながら、その行動範囲や素行を調べるんです。ときには捕獲して腹の中を捌いたり、機械をくくりつけて放して行動範囲を調べたりすることもあります。いわば野生動物を相手にした“探偵業”なんて説明をすることもあります。人間相手の場合と違って、彼らは言葉を持っていないから直接彼らの声を聴くことなどはできませんが、いろんな痕跡を見つけて丹念に調べていって、その生活を暴いていくわけです」...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 自然を守るには、身近な生活の環境やスタイルを変えていく必要がある
- 2012.05.08UP [自然を守る仕事 007]
 学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校
学校法人東京環境工科学園 東京環境工科専門学校 - 千葉県は、日本の酪農発祥の地で、現在でも乳牛の飼養頭数は全国第3位。なかでも銚子市は県内随一の“畜産のまち”で、特に酪農ではなく肉牛生産が盛ん。“畜産のまち”は、反面として家畜糞尿の処理に悩まされてきた歴史がある。...[続きを読む]

- ジャンル:学ぶ
- 卒業研究を通して学ぶこと
- 2012.03.13UP [大学で学ぶエコ・2 008]
 栗栖 聖 さん
栗栖 聖 さん - 大学生になって初めて自分ひとりで研究というものに取り組み始めるのが、卒業研究ではないでしょうか。都市環境工学コースでは4年生の5月に各研究室からテーマが提示され、そのなかから自分の興味あるものを選び、所属研究室を決定します。...[続きを読む]
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.