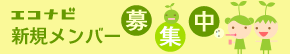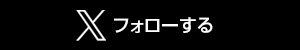- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 暮らし
- 暮らしに役立つ食と防災
- 008 食べた後のことを考える
0082025.10.21UP食べた後のことを考える
災害時の食の備えというと、「何をどれだけ備えるか」が話題の中心になりがちです。けれども、食べた後にどんなことが起こるか、どんな準備が必要かを考えておくことも大切です。これは、災害関連死を防ぐためにも欠かせない視点です。
私は災害食の講演で、「食べた後のことも考えてほしい」とお話ししています。特に、口の中のケア・ごみの処理・排泄などは、私たちの健康と環境に直結する大切な課題です。
今回は、食べた後に焦点を当て、災害時にも快適で衛生的、そして環境にやさしい備えについて考えます。限られた資源を上手に使い、食品ロスやごみを減らす工夫も「環境にやさしい備え」の一つです。
備えておきたいオーラルケア(口腔ケア)用品
災害時には、停電や断水、物資の不足などにより、口腔ケアがおろそかになりがちです。断水が続くと、歯みがきをしないまま過ごす人が多くなり、口の中の細菌が増えて誤嚥性肺炎のリスクが高まります。誤嚥性肺炎とは、口の中の細菌が誤って肺に入り起こる肺炎のことです。まずは「口の中を清潔に保つ」ことを意識してください。
今年9月に新潟市の朱鷺メッセで開催された「ぼうさいこくたい2025」(防災推進国民大会)に2日間参加し、「災害関連死を減らすには~避難所生活を分析してみよう~」という日本災害医学会のワークショップに参加しました。過去の大規模災害では、長期にわたる避難所生活の報告から、誤嚥性肺炎が災害関連死の主要な原因の一つとされています。特に高齢者に多く、発災から3か月以内に多くの命が失われています。ワークショップでは4人1組になり、意見を出し合いながら高齢者の避難生活における誤嚥性肺炎の原因を探りました。口の中の清潔さは間違いなく重要な要因の一つです。
特に、柔らかい食べ物を食べた後は口の中に食べかすが残りやすくなります。被災して疲れているときは、おかゆなどのやわらかい食品を好む傾向があります。おかゆは水分補給にもなり、体にやさしい食品ですが、続くと噛む機会が減ってしまいます。意識して、切干大根や以前ご紹介した玄米ごはんなど、やや硬めの食材を取り入れてよく噛むようにしてください。唾液の分泌が促され、誤嚥性肺炎の予防や血流改善、脳の活性化にもつながります。ただし、歯や歯ぐきに不安がある方は無理をせず、自分に合った方法で行ってください。
水が少ないときは、歯ブラシを軽く濡らして歯みがき粉を使わずに磨くのがおすすめです。口をゆすぐ際は、たくさんの水で1回するより、少ない水で2回行う方が汚れを落としやすいといわれています。歯ブラシがない場合は、水やお茶で口をすすいだり、ウェットティッシュで歯の表面を拭くだけでも効果があります。
液体歯みがきや歯みがきシートを備えておくと、断水時にも安心です。これらの衛生用品は、未開封であれば多くの製品が製造から約3年を品質保持の目安としています(ただし製品によって異なります)。私は3年を目安に入れ替えて使うローリングストックを心がけています。開封後は乾燥や揮発で効果が落ちやすいため、できるだけ早めに使い切るようにしましょう。
また、災害時のストレスによって唾液の量が減ることもあります。唾液が減ると口の中が不潔になりやすくなるため、よく話して笑って、口のまわりを動かすことを意識してください。口の中を清潔に保つことは、健康を守るだけでなく、災害時の生活の快適さにもつながります。
ゴミ対策も必要です
災害時には、ゴミ収集が止まり、ゴミをしばらく家に保管しておく場合があります。生ごみや、断水時には使用後の携帯トイレもあるかもしれません。そんなとき、家にある蓋つきの衣装ケースやコンテナを活用できます。もしもの時は中身を取り出して、空にしたコンテナに生ゴミや汚物を入れ、しっかり蓋を閉めるだけで、簡易的な蓋つきゴミ箱として役立ちます。さらに、消臭シートや除菌・抗菌スプレーを併用すれば、臭いや衛生面のリスクを減らすことができます。
普段使っているものを非常時にも活用することは、フェーズフリーの考え方にもつながります。まずは災害時も平時と同じように「ゴミを減らす意識」を持つことが大切です。日常で「食べきれる量を作る」「残った食材をアレンジして使う」といった工夫を習慣にしておくと、非常時にも役立ちます。こうした工夫は、食品ロスの削減や環境負荷の軽減にもつながり、「環境にやさしい備え」として日頃から取り入れておきたい視点です。
トイレ対策も忘れずに
排泄のことも、災害時にはとても重要です。トイレの衛生状態が悪くなると、できるだけ行かないように水分や食事を控える人が増えます。その結果、脱水や栄養状態の悪化、血栓によるエコノミー症候群など、命に関わる事態を招くこともあります。災害時のトイレ対策は絶対に必要な備えです。
私は10年以上前から災害時のトイレについて研究を続けており、2016年8月には日本災害食学会で「命を守る災害時のトイレ」というテーマで発表しました。
1週間、自分の尿量を計測し、汲み置きの水で処理してみたり、さまざまな市販の携帯トイレを購入して比較したりしました。猫砂や新聞紙、オムツなど、家にあるもので代用できるかも実験しました。さらに、「臭わない袋」は本当に有効かを確かめるため、それぞれの袋にキムチを100gずつ入れて6年間においの変化を観察したこともあります。小さかった息子にも協力してもらい、使い捨て傘ポリ袋で用を足す実験をしたこともあります。
食べ物に好みがあるように、トイレも人によって好みが違います。携帯トイレの袋の色ひとつ取っても分かれます。私は尿の色で体調を確認したいので「白派」ですが、友人は「汚物は見たくない」と言って「黒派」です。このように、自分の好みを知ることも大切な備えです。
まずは、1日に何回トイレに行っているか数えてみてください。トイレットペーパーをどのくらい使っているか測ってみるのもおすすめです。携帯トイレを備えたら、ぜひ一度、実際に使ってみてください。停電を想定して、夜、暗い中で試してみると、ランタンの必要性やトイレットペーパーの使い方、汚物の捨て方、手洗い方法など、多くの気づきがあるはずです。「携帯トイレがあれば安心」ではありません。自分で試し、体験しておくことが本当の備えにつながります。
災害時の備えは、命を守るだけでなく、環境を守ることにもつながります。普段から資源を大切に使い、食品ロスやごみを減らすことを心がけることが、環境にやさしい防災の第一歩です。食べることも、片づけることも、排泄も、すべてが私たちの暮らしの一部です。だからこそ、非常時にも「いつもの暮らし」をできるだけ続けられるようにしておきたいですね。
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.