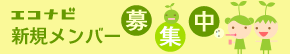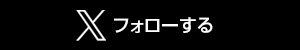- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 暮らし
- 暮らしに役立つ食と防災
- 007 備蓄食品の選び方&おいしく食べる工夫
0072025.08.19UP備蓄食品の選び方&おいしく食べる工夫
近年の災害の多発や気候変動の影響を受けて、「食の備え」はますます重要になっています。前回は「在宅避難 防災食の備え3か条」として、災害時に備えるための基本的な考え方をお伝えしました。今回は、在宅避難時のための具体的な備蓄食品の選び方や、日常でおいしく食べながら備える工夫をご紹介します。
在宅避難の食の備えは「いつもの味」から
非常時のために特別な非常食だけを買いそろえる必要はありません。大切なのは「普段食べているものを、非常時にどうやって食べるか」という視点です。ライフラインが止まっても、カセットコンロとボンベ、水、そして食べ慣れた食材があれば、工夫次第で温かい食事は可能です。
災害のために特別な物を買わなければと思う方も多いですが、自宅にある米、パスタ、餅、レトルト食品、缶詰なども立派な備蓄。いつもの食材が、もしもに役立ちます。これらを家族構成や体調、好みにあわせて備えることが大切です。また、アレルギーや持病、高齢者や乳幼児のいる家庭では特に注意が必要です。2週間分以上を目安に備えておきましょう。
さらに、「あたためなくても食べられるか」「水やお湯が必要か」といった、災害時の調理環境を想定しておくことも忘れずに。電気やガス、水道が使えない状況でも、すぐに食べられるものが少しでもあると安心につながります。我が家では、レトルトおかゆ、パンの缶詰、常温保存の豆腐など、“火も水も不要”な食品を混ぜて備えています。
普段から“おいしく試食”して備えに
実際に日常で備蓄食を食べてみると、災害時の安心感はぐっと高まります。
私が監修したフェーズフリー認証のレトルト食品「まゆまゆHokkori玄米ごはん」を職場の机に置いていた友人から連絡がありました。「お腹が減ったとき、そのまま食べたらおいしくて助かった!」とのこと。スプーンや箸さえあればすぐ食べられるとわかり、その簡便さに気づいた友人は、その後も何回か食べたそうです。「3つの味のうち、私はとりごはんが一番好き!」と言われ。こうした日常での試食は、味や食べ方を知るだけでなく、もしもの時の実践練習にもなると感じました。
3色食品群で栄養バランスをキープ
災害時でも健康を保つためには、栄養バランスの良い食事が大切です。そのために意識したいのが「3色食品群」です。これは食品を栄養素の働きによって「赤」「黄」「緑」の3つに分類する方法です。
赤の食品(体をつくるもと) … 主にたんぱく質を多く含む
例:魚・肉の缶詰、大豆製品(高野豆腐、納豆など)、卵、チーズなど
黄の食品(エネルギーのもと) … 主に炭水化物や脂質を多く含む
例:ごはん、パン、乾麺、餅、油、シリアル、クラッカーなど
緑の食品(体の調子を整える) … 主にビタミン・ミネラル・食物繊維を含む
例:野菜ジュース、乾燥野菜、海藻、果物缶詰、ドライフルーツ、乾物など
給食のように、各色からバランスよく取り入れることを意識すると、栄養バランスは整います。私が保育園の管理栄養士をしていたとき、食育活動で園児たちと3色食品群を使って栄養バランスについて考える時間がありました。園児たちは食べ物の見た目の色で考えるので、「トマトは赤色グループ!」「牛乳は白色グループだよね?」と元気に答えてくれたのが、今でも微笑ましい思い出です。
余談ですが、能登半島地震の被災地のニュースで、救援物資を3色食品群に分類し、「各色の食べ物からそれぞれお持ちください」と貼り紙をしていた避難所がありました。とても感動し、在宅避難でも避難所でも栄養バランスを意識することの大切さを改めて感じました。
常温保存できるタンパク質は“安心の種”
特にご高齢の方は「低栄養」に注意が必要です。常温保存可能なタンパク質は、停電や冷蔵庫が使えないときにも心強い存在です。
例:サバやツナの缶詰、親子丼・牛丼のレトルト、さきいかやサラミ、高野豆腐、常温保存の牛乳や豆腐など。
講座で常温保存できる豆腐を見せると、必ず「えっ、これ常温で大丈夫なの?」と驚かれます。未開封なら約5か月保存でき、水分が多く食べやすいので、高齢者や子どもにもおすすめです。ローリングストックにすれば、期限切れによる廃棄も減り、食品ロス削減にもつながります。
常温保存豆腐は、スーパーでは冷蔵コーナーの豆腐と一緒に並んでいることが多く、気づかずに冷蔵庫で保存している方も少なくありません。わが家では本棚に常温のまま並べておき、冷奴で食べるときは冷蔵庫に移します。鍋料理に使うときは、本棚から直接取り出してそのまま投入。こうしておくと、省スペースで保存でき、冷蔵庫の負担も減らせます。
常温保存できる野菜を忘れずに
避難生活でよく聞かれる悩みのひとつが「野菜不足」です。便秘や口内炎などの体調不良を防ぐためにも、野菜の備えは欠かせません。
じゃがいも・にんじん・玉ねぎなどの根菜類は日持ちしますが、断水などで調理が難しい場合には、そのまま食べられる野菜系食品が重宝します。
<おすすめの野菜系備蓄食品>
野菜ジュース・トマトジュース(ビタミン補給と水分補給を兼ねられる)
乾燥野菜(湯戻しで手軽)
ドライパックの缶詰・パウチ(例:大豆、ひじき、ミックスビーンズ、コーンなど)
ドライパックとは、高温の蒸気で容器ごと蒸し上げる製法のことで、調理時に水切りの手間や廃棄部分がなく、生ごみも減らせる環境にやさしい備蓄品です。
乾燥野菜やドライパック食品は、普段から料理に取り入れて調理に慣れておくことが大切です。切る手間もなく時短になり、日常の料理にも役立ちます。日頃から活用しておくことで、非常時にもスムーズに使えます。
私のお気に入りはドライパックのひじき。サラダや和え物にそのまま加えたり、煮物や炒飯にも活用できます。戻す手間がなく、すぐ使えるのが魅力です。また、ドライパックの大豆にふりかけを混ぜるだけで、おいしい簡単おかずになります。非常時だけでなく、忙しい日常の食事にも大活躍です。
美味しく食べるひと工夫
「口に合わなかった」食品も、ちょっとの工夫でおいしく変わります。
調理法:焼き目をつける、温める
味変:マヨネーズ、酢、ポン酢、ラー油、スパイス類
トッピング:チーズ、ツナ、コーンなど
講座では、カンパンにマヨネーズやケチャップをちょい足しただけで「おかわり!」が続出です。メープルシロップやジャム、ゆであずきのちょい足しも大人気。硬いときは果物缶のシロップに浸すと食べやすくなります。工夫を楽しみながら美味しく召し上がってください。
“備える・食べる・買い足す”を暮らしの中に
防災食は特別なものではなく、日常の延長で「備える → 食べる → 買い足す」のサイクルを回すことで、期限切れによる廃棄も減り、環境にもやさしい備えになります。
たとえば「週末は備蓄食デー」などを習慣にして、楽しみながら実践してみてはいかがでしょうか。無理なく続けられる工夫を見つけて、日常に自然に溶け込ませましょう。ぜひ、ご家庭でできることから始めてみてください。
フードバンクも活用
私はローリングストックをしながらフードバンクも活用しています。賞味期限が切れる前に食品を寄付し、必要とする誰かに使ってもらうことで、食品ロスを防ぎ、社会の役にも立てます。こうした循環は、災害への備えと環境配慮の両方を実現できます。身近なところから始められるので、お近くのフードバンクをチェックしてみてください。
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.