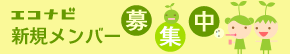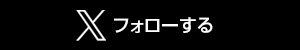- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 暮らし
- 島と自然と生きる人びと
- 007 その数20万本。島の椿を通し“子供が帰ってくる島”を作りたい
0072018.02.13UPその数20万本。島の椿を通し“子供が帰ってくる島”を作りたい-東京都利島村・加藤大樹さん-
東京から約140km、隣りにある伊豆大島とは20km程度しか離れていない周囲8kmの小さな島、利島。平地が少ないために空路は大島からのヘリのみ、湾がないので長く堤防を伸ばした港は波風の影響を受けやすく、メインのアクセスとなる船の就航率は5割程度だ。そのため訪れる人は観光というより釣り客が多く、昔ながらの暮らしや風景が今も残る穏やかな島である。
ところがこの数年、利島には20?30代の若手の移住者が増えている。若者たちは何を目指しやってくるのだろうか。
ネット求人広告で知った利島へ移住
利島を特徴づけるのはなんといっても椿だ。伊豆諸島が椿油の生産地であることはよく知られているが、最も多くを産出しているのが利島なのである。島の約80%が椿林で、その数はなんと20万本とも言われている。椿油の生産量は市町村レベルで日本一である。集落以外のあらゆるところに椿畑があり、椿油の原料となる実を収穫する秋ともなると、畑では実を収穫する人々、集落では軒先で収穫した実を日干しする人々の様子を見るようになる。
「農業から派生して、産業を拡大したい、そう思って利島に来ました」
2013年に家族で島に移住してきた加藤大樹さんは言う。埼玉県秩父郡長瀞市の出身。28歳まで都内で美容師をしていたが、徐々に故郷の人口が減り元気がなくなっていく様子を見て、「地元に貢献する仕事をしたい」と農業法人へ転身。今でいう六次産業化を目指した。しかし、生産者が苦心して作物を育てても、それに見合う収入が得られない構造を目の当たりにして疑問を持った。
「まずは生産者が再生産するための収入(再生産可能価格)を得られるにしないといけない」と痛感した。まずこの仕組みづくりに取り組める環境はないかと求人媒体を見ていたところ、東京島しょ農業協同組合利島支店の募集を見つけたのだ。
ここならすでに島中に20万本もの椿という原資があり、生産量日本一という長年の実績もある。自分がやりたいことが実現できる素地があると確信し、移住を決めた。妻も移住には賛成してくれて問題はなかったが、夫婦の気がかりはちょうど小学校入学となる子どものことだった。
「同級生がいるのかな? 一人だけだったらかわいそうだなと思って調べたら、7人同じ学年の子がいるのが分かって。それなら大丈夫だねと、一家で移住することになったのです」
ヤブツバキ原料の高品質椿油
加藤さんをひきつけた利島の椿油は、日本各地で生産される椿油の中でも特に高品質で知られている。都会のドラッグストアなどには「ツバキ由来」「椿オイル」などの表示がある美容製品があるが、本来、椿油と名乗れるのはヤブツバキの実で作られた油のみだ。利島の椿の木はすべてヤブツバキ。ユチャなど他のツバキ科の実から取れる油はカメリア油と言われ、区別されている。
椿油は悪玉コレステロールを下げるとされるオレイン酸の含有量が84?85%にものぼる。オリーブオイルでさえ75%と言われるのだから、その質の高さが伺える。
利島では島面積の80%が椿林と言われているが、畑となっているところはすべて所有者が決まっている。農家は47軒、農協に出荷している農家がそのうち40軒だという。
椿の実は木から直接採らず、地面に落ちたものを拾って収穫する。収穫期が近づくと、畑の持ち主は草を刈って実を拾いやすくする。落ち始めたらかがんで拾う人もいれば、落ち葉や石も含めてざっくりまとめてから大ふるい、小ふるいにかけて唐箕(とうみ)でゴミを飛ばして実だけを取り出す人もいる。
秋口、加藤さんに案内してもらって畑を訪れると、ふるいで実を取り分けていたご夫婦が「このあとは角ザルにあけて天日干し。それから袋に入れて出荷するから、結構手間が掛かるんですよ」と、手を休めずに話してくれた。
出荷のときには400kg単位で農協へ持っていく。農協では農家ごとに搾油を行い、それぞれの搾油量に応じて買い取りする。最も収量が多い農家では1年に350万円前後の収入があるそうだが、それは豊作の時の、熱心な農家の最高額だという。
利島と椿の歴史は古く、江戸時代にはすでに椿油を収穫していたらしい。平地がなく、なにより水源がなく水不足に苦しんできたこの島では、年貢もコメではなく絹織物を献上していた。しかしいつからか椿の実や油を年貢として収めるようになり、ちょうど江戸の女性たちの間で椿油で髪を整えることが流行したこともあって、特産物として盛んに江戸へ出荷された。
「昔から質がいい油として重宝されていたのだと思います。現在も出荷先の中心は8割が卸で、最終的には化粧品に多く使用されています」
椿畑の間を歩きながら加藤さんが話す。いずれは2割の直販売を拡大し、利島ブランドの製品も作りたいし、海外からの需要にも応えたいと加藤さんは考えている。
まだまだ解明されていない、椿の生態
では利島全体でどのくらいの収量があるのだろうか。すると毎年確実にこれだけ採れるという量がなかなか読めないのだという。
実は、椿とはどういう生態の植物か、まだまだ解明されていない部分が多いのだそうだ。
「畑の手入れって、基本的には草刈りと収穫だけなんです。でも、同じような環境の畑でもAさんの畑はたくさん採れてBさんの畑は少ない。その違いは何か? 剪定が必要なのか、日照量なのか、それとも別の要因か。そもそも、樹齢何年まで製品化可能な実が取れるかという正確な経済樹齢も不明なんです」
さらに、他の作物が表作、裏作という豊作と不作の年があるのと同様に椿にもそのサイクルがあるのだが、他の作物のようにそれが隔年で起きるわけでもない。ある年は1600斗(約26400kg)取れたが、取れない年は250斗(約4125kg)だったりする。収量がどのくらいか見込みが立たなければ商社や企業との取引がやりにくい。
「今、1つ1つの課題に取り組んでいて、いかに効率化して収量を上げていくかを考え中です。昔は薪としても椿を使っていたので、植えるときは密生させて、生長すると合間を間引いて薪に使った。それで木が横に伸びることができましたが、今は薪を使いませんから密生したままなので、木がすごく高く大きくなっています。葉っぱの量も少なくて、木自体が循環していないものもあるかと思います。そういうこと1つ1つがどう収量に関係するかを解き明かそうとしているのです」
そのために加藤さんは一軒一軒農家を訪ね「どの畑でどのくらいの実が取れたのか記録してください」とお願いしているという。こうしたデータが出揃って初めて「こういうふうに手をいれるとこれだけ収量が上がりますよ」と示すことができるのだ。
逆に言えば今までそういうことをしないでも成り立っていたのはさすが20万本椿がある島だとも言えるのだが、みんなが椿できちんと食べていけるような産業として成長させるためには、かなり大変な作業だが、この謎の解明が欠かせない。
こうしたデータ解析ができれば、やがて若者が島に戻ってきたり移住してきたりするときの仕事の選択肢としても椿が有力になってくる。
利島に若者が来る理由は
利島も多くの離島と同様、高校卒業と同時に若者が島から本州の大学なり専門学校なりへ出ていってしまう。若い世代が戻ってくるためには仕事が必須である。椿油の収量が上がれば出荷も増やせるし、島内で六次産業化して加工品なども展開できるのだ。
大量に観光客が訪れて島を消費していくような形の活性化より、そこに暮らす人々の生活をより充実させ、その幸福度を高めることで移住者が来るような、そういう形のほうが利島には似合っているように思う。そのために、椿は島の素晴らしい資源となる。
やりたいことはまだまだあると加藤さんはいう。
「野菜の島内消費アップもやりたいですね。島で作られている野菜はいま、ほぼ自家消費用なんですが、農協で毎年4品目ぐらいについて講習会を開いて、栽培品種を増やそうと力を入れています。たとえば学校給食に島の野菜を出しましょうよとお話してるんです。お孫さんの給食の野菜を作りましょうよってね」
子どもたちは約30人、先生たちを入れても60人ぐらい。それならば十分に島内でまかなえるだろうし、作る方も張り合いが出る。
夢の実現に一歩一歩、自分の考えを基に取り組みトライできる環境がここにある。もしかしたら、ほかの島や本州の中山間地域では誘致してもなかなかやってこない20?30代の移住者がこの島に来るのは、島のスケール感によって個人の挑戦が形になりやすいからなのかもしれない。
埼玉の農業法人ではできなかったことが、この島でなら実現できるはず。今までのキャリアを活かして次の展開を自分の手で作り上げる。島だからこそつかめるやりがいがあることを、加藤さんの生き方から教えてもらった気がした。
このレポートへの感想
利島の「椿油」のことが知りたくて このレポートを読みました。利島のことも分かって 良かったです。どんなに気をつけていても 度々ひどい「手荒れ」になっていましたが、利島の「椿油」を爪と手に塗るだけで 全く手が荒れません。本当に感謝しています。利島の椿を見に行きたいです。
(2018.10.13)
バックナンバー
- 001「人間を拒絶し続けた無人島・南硫黄島で12日間の自然環境調査!」
- 002「ハワイと八丈島をつなぐ未来への道(前編)」 -八丈島 栗田知美さん-
- 003「ハワイと八丈島をつなぐ未来への道(後編)」 -八丈島 栗田知美さん-
- 004「クロアシアホウドリが八丈島の未来を変える?!」 -八丈島 岩崎由美さん-
- 005「火山と生きる 自然と生きる 伊豆大島」
- 006「人が集まり大きなうねりを作る陸の“ナブラ”を作った人」 -新島・梅田久美さん-
- 007「その数20万本。島の椿を通し“子供が帰ってくる島”を作りたい」-東京都利島村・加藤大樹さん-
- 008「小笠原はなぜアカガシラカラスバトを増やせたか?」 -飼い主側から見てみると-
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.