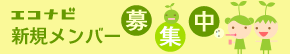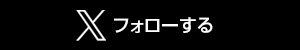- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 出かける
- 自然保護の現場から ~アメリカ国立公園滞在記~
- 007 人の手で守る自然
エコレポトップページへ
自然保護の現場から ~アメリカ国立公園滞在記~
「自然保護の現場から ~アメリカ国立公園滞在記~」バックナンバー
0072025.03.11UP人の手で守る自然
流域の再生
「レッドウッズ・ライジング」は、森林生態系全体の再生を目指す壮大な取り組みです。前回は、木の間伐による森林の再生プロジェクトを紹介しましたが、それ以外にも伐採前の河川環境を復元するための取り組みも行われています。
レッドウッドが皆伐された時代には、切り倒した木を搬出するため森林内に無数の作業道が作られました。作業道は、沢をせき止めるなど地形を無視して作られ、土壌流出を引き起こすことにつながりました。これにより、サケをはじめとする魚類の生息地が失われるなど、環境改変を引き起こしました。そのため、「レッドウッズ・ライジング」では、かつての地形を復元し、水域環境を再生するため、ロード・リムーバルと呼ばれる作業道を撤去する作業を行っています。
この作業も、木の間伐と同様、夏場に重機を使って行われます。そのため、レッドウッド滞在中に実際の作業を見ることはできませんでしたが、前年に作業した場所を案内してもらいました。現地は、一見すると荒れているように見えますが、沢に水が流れており本来の水流が復活しています。今、水が流れている場所は、もともと土砂が盛られ車が通る作業道になっていました。そのため、ショベルカーを使って、土砂を撤去する、また本来の傾斜を再現するため道路により削られた斜面に土を盛るといった作業が行われました。また、周辺に生えていた木は伐って、土砂が流れないよう倒木を地表に残し、自然に次の世代の木が再生するのに任せます。自然にはレジリエンスがあり、自ら再生できるように手助けするという発想で事業が行われています。
こういった作業道の撤去により、森の環境が再生できているか検証するため、国立公園の水域環境のチームが、下流の川の水量、流出する土砂の量などを把握するモニタリング調査を行っています。雨が降る冬が調査シーズンなので、水流を測る調査の手伝いもさせてもらうことができました。冷たい川のなかで、水速を測る機械を定点で保持して、データを取るという忍耐が必要になる調査ですが、周りを見渡せば、コケが生えていたり、ビッグ・リーフ・メープルと呼ばれる背の高いカエデの木からコケがぶら下がっている自然に囲まれています。国道からそれほど遠く離れていないのに、このような原生的な自然が残っているアメリカの国立公園で働ける喜びを感じました。

1960年代の空中写真
林内に作業道が張り巡らされていることが分かる。
(出典:米国国立公園局ウェブサイト)
自然に手を入れて保護するという発想
「レッドウッズ・ライジング」は、大学や他の行政機関からの視察も多く周囲でも注目されているプロジェクトです。3月にアーケータ(Arcata)にあるカリフォルニア州立ポリテック大学の環境科学専攻の学生を対象にしたフィールド授業に参加する機会があり、今に至るまでの歴史を学ぶことができました。上司のジェイソン(005「レッドウッドに到着」に登場)が講師となり、レッドウッド国立州立公園における森林再生の取り組みやその歴史を解説してくれました。興味深かったのは、再生の取り組みに理解が得られるまで、長年の時間がかかったということです。
1978年の国立公園拡張を機に、森林再生の手法として間伐実験が開始されましたが、再生のためとはいえ、木を伐採するという取り組みには、国立公園局の幹部や地元の保護団体から反対があり、翌年に実験は中断されます。その後、20年ほど経ち、絶滅危惧のキタマダラフクロウが確認されたことから、森林再生の必要性が再認識され、間伐の実験が再開し、2018年に始まった「レッドウッズ・ライジング」という形に発展しました。
加えて、国立公園内にあるBald Hillsという草原の管理にも話が及びました。Bald Hillsは、かつてはユロック族などの先住民が、ドングリの採取や篭編み用の植物の維持のため伝統的に火入れをして草原が維持されてきた場所です。ただ、1930年代には野焼きが禁止され、草原だった場所に針葉樹が分布を広げ草原は縮小しています。ここ数十年は国立公園としても野焼きをして草原の維持をしようとしていますが、すでに木が生えた場所を草原に戻すのは難しいようです。
このように国立公園における自然管理の考え方は50年ほどの間に変遷をしてきました。「国立公園局のミッションは、自然資源と文化的資源を損なうことなく保護すると謳っている。かつて公園管理は、自然に手を加えずそのままにしておくという考え方が中心的だった。でも、人が手をかけないと守れない自然もある」とジェイソンは解説していました。
日本では、薪炭林の手入れや草原の野焼きなどを通じ、伝統的に人が関わることで維持してきた自然があります。そのため、国立公園においても、人が維持活動をすることで自然を保護している場所があります。それに対比して、アメリカの国立公園は大自然が多く、極力手を入れずに保護されているのではと私も思っていました。しかし現場では、レッドウッド国立州立公園のように、アメリカでも、先住民の伝統的な自然の管理方法を、国立公園の管理者が参考にし、野焼きを再開するなどの動きもあることは学びになり、また自然に手を加えることが肯定されていると知って新鮮に感じました。
Bald Hillsでの調査
Bald Hillsの草原には野生動物関係の調査で何度か訪れる機会がありました。一つは、野焼きの影響により、ネズミなどの小型哺乳類の増減があるかを調べるため、その捕食者である猛禽類の数を調べる調査です。舗装が荒い車道を登っていくと、森が開け、草原が広がります。定点ポイントで車を停め、調査に慣れた国立公園の職員が、アカオノスリやアメリカチョウゲンボウなど鳥の種類を記録していきます。
また、別の日には、ルーズベルト・エルクという大型のシカ類の個体数調査にも参加しました。エルクは、州政府の魚類・野生生物局が管轄する狩猟鳥獣であり、狩猟できる個体数に制限が設けられています。捕獲可能個体数が少なく、ハンターがライセンスを得られるのは10年に1度などと、かなりまれなようですが、この捕獲可能個体数が適正であるか、州政府の調査に協力する形で国立公園内の個体数を調査しています。調査では、エルクの群れを発見したら、群れの個体数と性構成を記録していきます。カリフォルニアでは、数年前より、エルク蹄病が蔓延しており、エルクの個体数は減少していると言われていますが、私が参加した調査では、前年とほぼ同じ結果が得られました。
車を購入
生活関係では、初めの数か月は、行政手続きや金融関係など基盤を整えるまでが大変でした。車関係は、出国前に日本で取った国際免許証で、レンタカーは問題なく借りることができましたが、カリフォルニア州では短期の旅行者以外は州の免許証を取る必要がありました。免許証取得には、まず筆記試験に合格し、Learner's permitと呼ばれる仮免許をもらいます。仮免許があれば、助手席に免許証を持っている人が乗っていれば公道で運転することができるので、親などの車で練習し、その後、実技テストを受けるのが一般的なようです。
まずは1か月ほど、筆記試験に備えカリフォルニア州の交通法規を勉強しました。日本との違いは、右側通行であることの他にもたくさんありました。赤信号での右折(日本だと左折に該当する小回りの方)も周囲の状況が安全であれば基本的に可能であること、少量の血中アルコール濃度であれば飲酒運転も可能であることなど、なかには驚くような内容もあり勉強になりました。オンライン上に出回っている模擬試験を解いて練習し、筆記試験は無事合格することができました。次の実技試験は、日本で何年も運転しているので大丈夫だろうと思っていましたが、一旦停止の後にゆっくり走り過ぎと言われ不合格になり落胆しました。別の日に再度試験を受け、2度目で合格することができ、とてもほっとしました。2度目の試験官は、私の名前を見て日本人だと分かったようで、日本の大学に留学していたと、試験後に話をしてくれ、試験で緊張していた気が和みました。アメリカの免許証ができたことで、パスポートを持ち歩く必要もなくなったため、アメリカの生活基盤が一つできた感じがありました。
免許証が取れて、ひと段落したところで、車を買うことにしました。アメリカではスバルの評判が高く、日本よりスバル車がたくさん走っています。私も日本ではスバルに乗っていることもあり、アメリカではスバルのフォレスターを買うことにしました。当時1ドル150円~153円と円安が進んでおり、7年落ちのフォレスターが350万円近くと高い買い物でしたが、1年間大きな故障もなく帰国までお世話になることになりました。
購入したスバル・フォレスター
日系の中古車販売店から購入した。買って1か月以内に、2回もタイヤに釘がささるという事態にあったが、近所に無料で修理してくれるタイヤ店がありお世話になった。アメリカの車には、空気圧の警告灯が全車装備されているので、パンクする前に修理することができたので助かった。
(次回に続く)
関連リンク
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.