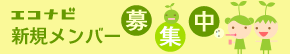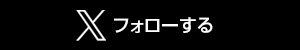- エコナビTOP
- 連載コラム「エコレポ」
- 暮らし
- 竹とあそぶ
- 004 地域で新たに立ち上げた文化的活動も、20年・30年と続けていけば伝統文化になる
0042020.03.24UP地域で新たに立ち上げた文化的活動も、20年・30年と続けていけば伝統文化になる-吉野ヶ里バンブーオーケストラ&さざんか塾-
ベージュ色に輝く竹楽器が、竹独特のやさしい音を響かせる
澄んだ音が響く、竹マリンバ。木製の架台に並べた長さの異なる竹筒を、マリンバ(木琴)と同じように、バチで叩いて音を出す鍵盤打楽器の一種だ。竹の一端に節を残して、開口部に2本の切り込みを入れることでベロ状のリードを作り、筒内の共鳴胴と音程を合わせることで、余韻のある竹ならではのやさしい音を響かせる。竹筒の径(太さ)や長さ、スリットの切り込み長などによって、音が変わってくる。竹のサイズによる音の高低の違いで、バス、アルト、ソプラノなどのセットを使い分けている。
竹楽器を作るには、調律器で音を測りながら、ベロ状に切り込みを入れるリード部分を加工していく。最後はノコギリ刃の1枚分ほどの厚みで調整して、竹筒1本1本の音を決めていく。それだけ慎重に調律しても、自然の竹を使っているから完成後にも室内の水分を吸ったり吐いたりして、湿度の変化によって半音くらいはすぐに変わってしまう。演奏直前には、会場内の湿度に合わせて、竹筒を締め付けたりして音の最終調律をする。
竹マリンバが竹筒の側面を叩いて竹の振動で音を出すのに対して、斜めに固定したマダケの開口部(竹筒の切断面)にゴムパッドを打ち当てて、筒をふさぐようにして空気の流れを作って音を鳴らす楽器を、マウイと呼ぶ。南太平洋で使われている楽器だ。こちらも、バスマウイ、小マウイ、竹筒を長くしたスーパーマウイなどの種類を使い分けている。
ロンドアラムと呼ばれる楽器は、両端に節を残した極太のモウソウチクを横向きに置いて、筒の垂直面に沿って1本の切り込みを入れた、竹のスリットドラムだ。竹の太さ、切込みの大きさによって音程を変えることができる。叩く場所も、スリットを入れた中央部だけでなく、竹節を横から叩くことで異なる音が鳴り、2本のバチで交互に叩くことで独特のリズムを刻むことができる。
このほか、アンクルンと呼ばれる2本の竹筒を枠に吊るして揺することで乾いた音を響かせるインドネシアやジャワに伝わる民族楽器や、日本の民謡や祭囃子などでも使われる和楽器の篠笛など、竹ならではのベージュ色に輝く美しくも珍しい竹楽器の数々が、バンブーオーケストラの楽器パートに名を連ねている。
平成18年3月1日に佐賀県北東部の三田川町と東脊振村が合併して誕生した神埼郡吉野ヶ里町で「バンブーオーケストラ」が結成されたのは、平成8年のこと。自然の竹を活用した創作楽器による日本初のアマチュア合奏団として大きな話題を呼んだ。発足時は当時の町名から「東脊振バンブーオーケストラ」として活動してきたが、合併を機に「吉野ヶ里バンブーオーケストラ」と名称を変更している。
「地元の資源を活かそう」「地域にねざした伝統文化をつくろう」と、佐賀県出身の篠笛・尺八奏者、柴田旺山さんの指導を受けて、翌平成9年に開催された『世界・炎の博覧会』で演奏したのが、初お披露目だった。以来、20年以上にわたり、演奏活動を通じて里山保全と竹との関係、竹の資源活用などについて発信を続けている。
現在は、小学校低学年から還暦を超えた大人まで約20名がメンバーに名を連ねている。中学生時代にブラスバンド部と兼ねて参加していた子が高校進学を機に離れていき、再び大学生になって戻ってきてリーダー的役割を果たす例もあるように、基本的に出入りは自由。20年の月日を経て、幼少期に演奏していた子が成長して結婚し、親になって、その子どもが小学生にあがったからと参加してくるケースもある。まったく新たに入会してくる子も含めて、世代をつないで活動が継承されている。
世界・炎の博覧会(せかい・ほのおのはくらんかい)は、平成8年(1996年)7月19日から10月13日までの会期で、佐賀県内の3会場を中心に開催された地方博覧会。正式名称は「ジャパンエキスポ佐賀'96 世界・炎の博覧会」。
梅雨時には、虫が湧いて、カビも舞う。
部屋の湿度によって音が変わるから、調律も大変だった
竹楽器というと、多くの人にとってすぐに思い浮かぶのは、篠笛(横笛)や尺八などだろうか。世界各地では、アジア諸国を中心に百種類を超える種類の竹(バンブー)楽器が使われているという。主に吹奏楽器(管楽器)や打楽器に使われているが、単に身近にあった素材という以上に、生活に根付いて重宝されていた竹を、音楽を奏でる楽器としても活用していた証と言える。
バンブーオーケストラの活動は、そんな身近な竹という素材で楽器を作ることができること、自分たちで音楽を作ることができることを知って、経験してほしいとの思いを込めて始まったものだった。
吉野ヶ里バンブーオーケストラの顧問で、立ち上げ当初からかかわってきた、さざんか塾の多良正裕さんが、楽器づくりやメンテナンスの苦労について話してくれた。
「一番最初に揃えたバンブー楽器は、山に生えている竹を子どもたちとノコギリを引いて伐り出すところから始めました。当時は炎博に出演することが決まってから急いで竹を伐りだしてきたので、青竹のまま油抜きもしないで楽器にしたんですね。使っているうちに蒸れて虫が湧いたりカビがついたりと大変でした。ちゃんとした保管場所もありませんでしたし、演奏活動に行くときにはトラックを借りて運搬するため、作りが雑だと搬送時の振動で緩んでしまうなど、課題が満載でした。今はキャスターも付けて運びやすくなっていますが、以前は重い竹楽器を持ち上げて移動させていましたから、演奏以外で男手が不可欠でした」
特に大変だったのが、楽器のメンテナンスだった。最初の演奏会では柴田旺山先生が調律もしてくれたが、東京在住の柴田先生にその後もずっと頼るわけにはいかない。誰かがちゃんと調律できるようにならないと続かないと言われて、もともと音符も読めずに力仕事の手伝いだけのつもりだった多良さんが、柴田先生の横について見よう見まねで覚えて、調律係を担うようになった。
「文化会館など大きいホールに行くと、その空気でどんどん音が変わっていくんですね。少なくとも半日か一日前に楽器を会場に持ち込んでおいて、最終的には演奏の始まる1時間前に最終調律をします。一つ一つ叩いて、ネジで締めたり緩めたりして…。それが私の役割だったんです。そういう裏方作業も、私だけではできないので、みんなで大変さを共有して、分担できるようになっていきました」
当初は手作りのよさもウリの一つだったといえるが、それから20年経って、今は天皇陛下をはじめとする来賓の前で演奏を披露するようにもなって、演奏技術を向上させてきたと同時に、楽器の見栄えも問われるようになってきた。現在の楽器は、佐賀県からの補助金で新調した3代目に入れ替えている。里山保全の一環で伐り出した竹を、メンバー・スタッフ総出で、磨いて乾燥させて、ニスを塗ってという作業を何度も繰り返した。時間はかかったが、ほどよく水分が抜けて、音の安定にもつながっている。
世界・炎の博覧会(炎博)の出し物がない!?
バンブーオーケストラの発足時から裏方作業を支えてきたのが、現在は多良さんもメンバーに名を連ねる「さざんか塾」だ。平成8年に佐賀県で世界・炎の博覧会が開催されることになった当時、多良さんは旧東脊振村役場の職員として、さざんか塾に炎博への協力を呼びかける立場だった。
「炎博では、各市町村が伝統芸能などを中心に出し物を担当することになりました。面浮立(めんぶりゅう)や太鼓などがあるところではそれに磨きをかけて披露すればよかったのですが、当時合併前の東脊振村ではこれといったものがありませんでした。役場の中だけで考えていてもよいアイデアは出てきませんから、さざんか塾に相談したのです。そうしたら、『ないんだったら作ればいい』と言われました。『新たに作って、それを20年、30年と続けていけば、伝統文化になろうもん』という発想です。だから、続けることが大事というみんなの思いで、いろいろと紆余曲折ありながら、ここまできました」
新たな文化を創るために、どんな活動ができるか。その頃、里山保全の取り組みの一環として放置竹林の問題に取り組んでいたこともあって、竹をテーマに考えてみようということになった。それを文化的な活動にまで昇華させるにはどうすればよいか。たまたま佐賀銀行の文化財団が、県内の企業メセナによる佐賀の芸術文化向上の活動の事務局を担っていて、毎年、佐賀県にかかわりのある芸術家を表彰・支援していた。表彰者の一人になった篠笛・尺八奏者の柴田旺山さんの経歴等を聞きとっていく中で、バンブージャパンという竹楽器を使ったプロ楽団で演奏活動をしているとともに、子どもたちを中心に竹と親しんでもらうための市民向けワークショップも実施して、自然環境教育に力を入れていこうとしているということが判明した。まさに竹をテーマにした文化活動を創り上げるための指導者としてうってつけの人物だと白羽の矢が立ったのだ。
「さっそく連絡先を聞いて、炎博で発表できるくらいまで面倒を見てもらえないかと相談しました。柴田先生も、当時は1日限りのワークショップとして竹楽器づくりと演奏をしているだけでした。アマチュアのバンブーオーケストラはまだ全国どこにもなく、結成したいという夢を持っていらしたので、全国初のアマチュア・バンブーオーケストラの立ち上げからかかわってくださいとお願いをして、縁ができたのです」
旧東脊振バンブーオーケストラの取り組みがモデルになって、その後、各地でアマチュア・バンブーオーケストラが結成されることになる。各地の活動を通じて、楽器の作り方や指導方法などにも改良が重ねられていった。こうした活動経験の蓄積は、オリジナルの活動にもフィードバックしている。現在使っている第3代のバンブー楽器が、運搬しやすよく見栄えもよい最新型として新調できたのも、各地に広がっていく中での経験が存分に生かされたことによる。
田舎の、何が資源かというと、人なんです。
“田舎”の資源は「人」だと多良さんは言う。都市に住んでいる人たちは、定年退職した後、それぞれの趣味に時間と情熱を費やすケースが少なくはない。一方、田舎では活動する場――言い換えればそこに住む人たちが手をかけなければいけない土地がふんだんにある。放っておけば荒廃していくばかりだからこそ、“故郷を守る会”などの活動が盛んになっている。団塊の世代のまだまだ元気な人たちがたくさんいて、山の環境保全活動に汗を流したり、学校で子どもたちに教えたりしている。吉野ケ里にはそんな地域性があるわけだ。さざんか塾は、まさにそんな人たちが集まって、住みよい街を作っていくための行動を起こして、活動を続けている。
さざんか塾結成のきっかけは、竹下内閣時代のふるさと創生事業の予算を使って、旧脊振村役場が地域の人材育成を目的として実施したソフト事業にあった。当時村役場の職員だった多良さんは、「地域興しの担い手を募集するので、誰か手を挙げてくれるような人を推薦してください」と村内の各区長にお願いするところから始めた。村のために何かせなと集まった人たちで結成した団体は、脊振山脈の中腹に広がって国指定の天然記念物にもなっている「千石山さざんか自生北限地帯」(約2.9ヘクタールに約2,200本が自生)にちなんで、「さざんか塾」と名付けられた。事務局を担った多良さんにとっては、行政内各部署との橋渡しや全国の活動の紹介といったサポート役としてかかわったのが最初の付き合いだった。
「さざんか塾の行動方針は、いろいろと考えるより、まずやってみようということ。それから、目先にとらわれずに、10年後、50年後、100年後を見据えた目線で、身近にできることから地に足のついた活動をしようということで取り組んでいます」
単に地域おこしの活動をこなしていくというのではなく、自己研鑽しながら自らを高めて、実践をする場所をめざしている。だからこそ、一人ひとりが活動するプランナーであり、それらの実現をまわりのみんながサポーターとなって育んでいく。その延長で今があるし、それゆえに30年以上にわたって活動が続いてきたともいえる。
竹に注目したのは、地域で邪魔者扱いされるようになってしまった竹も、見る角度を変えると資源じゃないかという発想だった。裏山の竹を伐って伝統芸能のない村に新たな伝統芸能を生み出すために、柴田旺山先生の指導の下、竹伐り作業や楽器製作を進める傍ら、演奏メンバーを公募した。足りない頭数は、音楽ができるメンバーの奥さんにも参加してもらってかき集めた。
日本初のアマチュア・バンブーオーケストラが炎博でデビューするということで注目され、九州一円で放映されるテレビ番組にも取り上げられて、楽器を作るところから初演までの密着取材を受けた。一気に名が知れるようになって、問い合わせや視察も殺到し、一時期はその対応にうれしい悲鳴を上げることになった。以降、さざんか塾は裏方に回ってサポートに徹してきている。
吉野ヶ里バンブーオーケストラでは、毎年秋には「竹ものがたり?竹・光・音のシンフォニー?」と呼ぶ自主企画の演奏会を開催している。他地域のイベントに招かれて出演するだけでなく、年に1度は地元の町民にもお披露目しようというもの。発足当初の第1回は、昼の部・夜の部の2部制にして、日中にはタケノコ掘りや竹の森の中での竹細工を体験してもらい、夜の部ではバンブーオーケストラの演奏を聴きながら、婦人会の協力で作ったタケノコ料理「竹御前」に舌鼓を打つという、まさに竹尽くしのイベントとして企画した。ただ、あまり詰め込みすぎても持続しないため、今は演奏をメインにしたイベント構成にしている。
その分、音楽の質にこだわった演奏会として、毎回プロの演奏家を招いて、いっしょに演奏している。柴田先生はもちろん、地元出身の若手音楽家に一年間かけて指導をしてもらって、その成果を披露するという方法をとっている。プロの音を聞きながら、自分たちの音も変わっていく。指導は厳しく小さな子どもにも容赦はないが、その分、楽譜の読めない小学校低学年の子どもたちも、必死になってついてくる。単に自分たちの演奏を発表する学芸会的な位置づけではなく、その道の第一人者とのコラボ演奏をすることで、音楽の質が向上していくし、子どもたちも自己肯定感が持てるようになっていく。
中国産タケノコの輸入でダメージを受けたところに入ってきたイノシシ
里山の荒れた竹林から竹を伐り出して、自分たちで楽器をつくって、オーケストラを結成したというストーリー性に注目が集まるが、毎年伐っているわけでは、実はない。楽器に使う分だけで竹林整備が進むということでもない。でも、だからこそ、バンブーオーケストラの演奏などを通じて、少しでも多くの人たちに資源としての竹に注目してもらい、それとともに竹が抱える問題について認識してもらいたいというのが、今の時代に合った伝統文化としてこの20年間継続して築き上げてきた、吉野ヶ里バンブーオーケストラとその活動を支えるさざんか塾のめざすところだと多良さんは言う。
役場職員としてバンブーオーケストラの立ち上げにかかわった多良さんは、その後、平成17(2005)年に東脊振村の最終代村長として、また同年3月の合併後には吉野ヶ里町議を経て平成26(2014)年4月から平成30(2018)年までの4年間、吉野ヶ里町長として地域全体のかじ取り役を担ってきた。
吉野ヶ里地域の竹の課題には、他地域と同様、中国産のタケノコの輸入とイノシシによる獣害が深刻化していった経緯があると多良さんは言う。
「中国産のタケノコが入ってきてお金にならなくなったことで、竹林の整備がされなくなっていきました。加えて、佐賀県の場合、昭和60年代に入って高速道路が鳥栖から長崎の方に向かって伸びていったのを境に、鳥栖方面からイノシシが入ってくるようになりました。それまでほとんどいなかったイノシシが、瞬く間に佐賀県一帯に増えていきました。特に、東脊振一帯は佐賀県の中でもいいタケノコの採れる産地でしたから、イノシシにとっては最高のえさ場になったのです。タケノコを採るために管理をしても中国産の安いタケノコに押されていく、しかも換金作物として最も価値の出る早い時期のタケノコを根こそぎイノシシに掘られてしまう。まさに踏んだり蹴ったりの状況です。ですから、竹を活かそうと思ったら、イノシシ対策も同時にやらないと先には進めなかったんですね」
そうして、イノシシ防除の柵を、数千万円の補助金をかけて林道沿いに設置したが、地元の農家の高齢化によって十分に管理できなくなっていくと、1か所あいた穴から入ってきたイノシシがすべてを荒らすことになる。対策として、防除だけでなく、駆除もきちんとせんといけんよねということになって、猟友会に委託して、有害駆除で捕獲していった。
当時、年間の捕獲頭数は7?800頭にもなったから、捕った獣肉は猟友会で消費できる量では到底ない。自然、山に打ち捨てていくことになり、水質悪化の原因になるなど山の環境にとって好ましい状況ではなかった。そこで、捕獲した分の適正処理にかかる経費については行政責任として、町が負担することとした。猟友会では、隣接する神埼市の市域を含む山一帯を管理していることから、神埼市と連携して、獲れた頭数に応じた補助制度を創設するとともに、ジビエとして処理するための施設を併設した「吉野ヶ里町さとやま交流館」を開設した。
「タケノコについても、特産品として出荷できるように、さとやま交流館の中にきちんとした品質管理の下で加工・調理のできる施設をつくりました。また、屋外にはご家庭で食べる分の処理ができるように、薪を焚いて採ってきたタケノコをすぐに湯がいて処理できるような設備も用意しました。出荷まで対応できる施設と、自家消費用の設備と両方を用意することで、地域で活用してもらえる施設にしたいということで造ったものです。まだ開館したばかりですが、今後はタケノコ部会など、地域の人たちが自立的に活動できるような体制を作っていきたいんですよ。地元の醤油屋さんとも話をして、炊き込みご飯用の具材に加工する計画も進めています。今の若い人たちは素材としてのタケノコだけでは食べてもらえませんから、すぐに食べてもらえるような商品開発までやっていかないと、特産品にはなりません」
今後、周辺の竹林を観光タケノコとして整備していきたいと多良さんは言う。屋外に設備した鍋には薪で沸かした湯を用意しておいて、施設を訪れる人たちが掘りたてのタケノコの皮をむいて、自由に湯がいて持ち帰れるようにする。地主さんが自分で整備してもよいし、組合を作って管理するのでもよい。いったん途切れた環をつなげるのは簡単ではないが、そのための設備はできたから、今後はそれを活用する実践段階にきている。
今、多良さんは町長の職も辞して、ようやく自分の住む地域の活動に専念できるようになった。続けていくと、何か次につながっていく。これまでは文化を創り上げていくのに手いっぱいだったが、やっと地域資源としての竹の活用に着手できるようになったと話す。
バックナンバー
- 001「森の竹を使ったセロ弾きの調べ」 -竹凛共振プロジェクト-
- 002「地域資源として竹を生かすため、セルフビルドの竹構造農業用ハウスをデザイン」 -京都大学「バンブーグリーンハウス(BGH)プロジェクト」-
- 003「“竹(バンブー)を楽しみ(エンジョイして)”、生きがいづくりに」 -香川県さぬき市「バンジョイ塾」-
- 004「地域で新たに立ち上げた文化的活動も、20年・30年と続けていけば伝統文化になる」-吉野ヶ里バンブーオーケストラ&さざんか塾-
【PR】
フッターメニュー
エコナビについて
サイトポリシー
募集・お問い合わせ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.